
森林セラピーというリトリート
リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...

冬の森林には、他の季節と異なることが多いです。落葉樹は葉を落とし、それにより、普段は見えない風景や隠れていた動物たちを目にする機会も増えます。また、寒さへの対応として、さまざまなことが行われています。なかなか冬に森林浴に行くという選択肢がない方も多いとは思います。冬だからこその楽しみもあるのではないでしょうか。
冬に落葉する木があります。どうして葉を落とすのでしょうか。
葉は光合成を行います。水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを利用して、デンプンをつくり、酸素を発生する反応です。このデンプンが樹木の成長の素になります。日照時間の長い夏には、この反応はどんどん進み、樹木はデンプンを蓄えることができます。冬には日照時間が減るため、この活動は少なくなります。また、乾燥する冬には、樹木の中の導管が凍って水が流れにくくなる現象を避けなければいけません。葉があると水分が失われやすいのです。それらのことから落葉樹は自ら葉を落とすのです。

葉を落とす前に、いくつかすることがあります。
まず、光合成を行う葉緑素やデンプンなどのエネルギーを葉から幹や根に移動します。これにより、寒い時期の活動や来年また光合成するための材料(葉緑素など)を保管することができます。その後、葉と枝の間に分離するための層(離層)をつくります。そして、その層のところから風などにより切り離されて、葉は落ちていくことになります。
葉緑素を幹や根に移動した後には、黄葉や紅葉があります。
いちょうの葉っぱが黄葉するのはカロテノイドという色素によります。ただ、この色素は秋になって作られるのではなく、葉っぱが緑色の時に既に作られていて、緑色の色素に隠れているのです。そして、緑色の色素が減っていくと共に黄色い色素が目立ってきて、黄色くなるのです。だから黄葉は毎年ほぼ変わりなく発生します。
カエデが紅葉するのはアントシアニンという色素によります。この色素は緑色の時に作られるのではなく、葉っぱの緑色のクロロフィルがなくなるにつれてアントシアニンという色素が新たに作られます。きれいに紅葉するための条件は2つです。1日の温度変化(昼は暖かく、夜は冷える)と太陽の光、特に紫外線がよく当たることです。毎年この条件は変化するので、紅葉は年によって色が変わるのです。
落葉しない常緑樹はどのような働きをしているのでしょうか。
1年中、緑色に輝く葉をつけている樹木は常緑樹と呼ばれます。落葉樹とは異なり、1年中光合成をしています。常緑樹も落葉樹と同じく、冬に凍ってしまうことを避けなければいけません。どのような工夫があるのでしょうか。
冬に向かってこれらの樹木は葉に糖分を増やします。これにより、凍りにくくしています。また、常緑樹の葉は、落葉樹よりも分厚く、ワックスなど水分の蒸発を防ぐ仕組みがあるものもあります。

落葉樹は冬になると葉を落とし、春になると葉をつけます。常緑樹は1年中葉をつけていますが、その葉っぱはどうなるのでしょうか。常緑樹の葉も生え変わるのです。ただ、毎年ではなく、樹種によって時期や方法が異なります。例えば、クスノキやシラカシは、4〜5月のうちの1週間位で全ての葉を落とし、新旧の葉が交代します。針葉樹は10月から12月にかけて、葉の古いものから順に落ちていきます。

落葉樹は晩秋に葉を落とし、休眠状態で冬を過ごします。春に再び芽吹き、活動を開始するために準備されたものが冬芽(ふゆめ・とうが)です。冬芽には、花になるもの、葉になるものがあり、それぞれ花芽(かが)、葉芽(ようが)と呼ばれます。冬の寒さや乾燥に耐え、病虫害から身を守るがさまざまな工夫がされています。例えば、コブシの冬芽は毛に覆われています。トチノキは虫を寄せ付けない水あめ状の樹脂で冬芽は覆われています。
参考図書
「植物学『超』入門」〜キーワードから学ぶ不思議なパワーと魅力 田中 修
「樹木たちの知られざる生活」〜森林管理官が聴いた森の声〜 ペーター・ヴォールレーベン
「冬芽ハンドブック」 解説 広沢 毅 写真 林 将之
参考ホームページ
森林・林業学習館https://www.shinrin-ringyou.com
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...
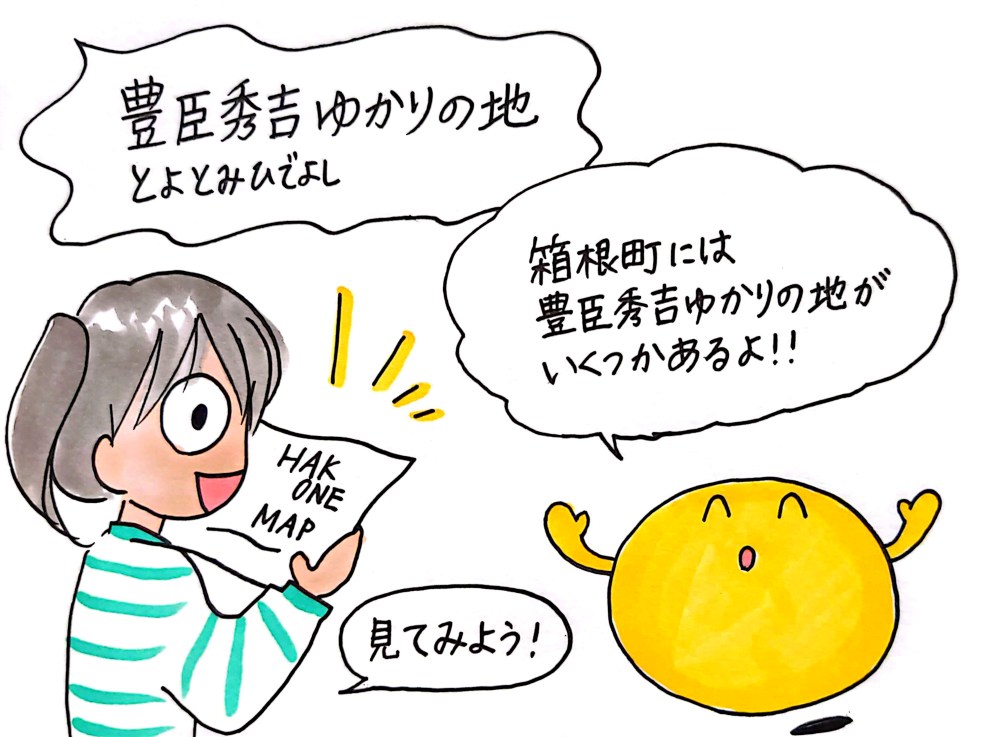
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...