
病気が教えてくれた「自然治癒力と予防医療」
予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

秋から冬にかけて森林は大きく姿を変えます。草花は枯れ、落葉樹は葉を落とし、
昆虫や動物も姿を見せなくなります。その中で動植物はさまざまな戦略で生存しています。
この時期だからこそ観察できることがあります。
1 寒い季節を乗り越える姿
2 さまざまなタネの戦略
3 越冬のためにやってきた冬鳥
1 寒い季節を乗り越える姿
寒くなると地べたに葉っぱを広げている草が目につきます。ロゼットと言われる姿です。
タンポポ、ギシギシ、オオバコ、ハルジオンなど多くの種類があります。
多くは、花の咲く時期に葉っぱは地べたから離れて上へ伸びていくのですが、秋から冬にかけては様子が違います。どうしてこのような姿になっているのでしょうか。
この姿は寒い季節を乗り切るのに都合が良いのです。
寒い風を避けることができ、地面の温かさを受けることができ、また、太陽を全面で受けられるので、光合成によりエネルギーを蓄えることができます。
そして、春暖かくなったときに、いち早く成長して花を咲かせるという戦略なのです。
 |
 |
2 さまざまなタネの戦略
この時期は多くの実やタネを見られます。次世代に繋ぐためのさまざまな戦略を紹介します。
動物や人にくっつく(付着散布)
人から「ズボンに何かついているよ」と言われて気づくなど、知らない間に服についているタネがあります。
いわゆる「ひっつき虫」です。コセンダングサ、ヌスビトハギ、チカラシバ、オナモミなどがあります。
トゲや微細な毛、粘液などで動物の毛や人間の服にひっかかります。そして、動物や人間に遠くにタネを運んでもらうのがねらいです。
このように運んでもらうとタネが落ちるのは、人や動物が歩く道沿いの明るい場所になることも植物にとっては利点ですね。
指で触ってもくっつきませんが、服で触れるとひっついてしまいます。ぜひ試してみてください。
 |
 |
風に乗って遠くに行く(風散布)
風を利用する植物は、なるべく遠くへタネを運んでもらうために、いろんな工夫をしています。
タンポポやプラタナスは、パラシュートのような形でタネを繋げていて、風に乗りやすくしています。
ケヤキは、タネが入った実と葉のついた枝がセットになって、木から切り離される仕組みになっています。
葉が風を受けて、タネと共に遠くへ飛ばす仕組みになっているのです。
カエデ類は、2個セットのタネが木についています。竹とんぼのような形ですが、飛ぶときには1個ずつで、それが回りながら落ちていきます。
回っている間に風に乗ることができれば遠くに飛んでいきます。下に落ちているタネを投げてみるとそのことがよくわかります。
 |
 |
他にもラン科のタネなどは、とても細かい粒子状のもので、風で飛びやすいです。
食べられることで運んでもらう(被食散布)
動物に実を食べてもらい、タネを糞などで出してもらうことで、遠くにタネを運んでもらう戦略もあります。
どの動物をねらうのかにより、色、形、香りなどを変えています。鳥ねらいの場合、鳥が食べられる程度の大きさで、色は鳥の色覚は赤に敏感なので、赤色が多く、次いで黒となります。
鳥は匂いには鈍感なので香りはないです。ガマズミ、ナンテン、クロガネモチ、ハナミズキなど多くあります。
まずい実や有毒な実もあります。これは一度に食べられないようにして、なるべく遠くへ運んでもらう仕掛けとのことです。
 |
 |
鳥以外の動物(哺乳類)ねらいの場合、哺乳類は匂いに敏感なので、香りがあるものが多いです。
人間が食べるフルーツ類はこのようなものが多いです。サル、タヌキ、テンなどが該当します。
食べ残してもらう(貯食散布)
ドングリやクルミなどは、哺乳類や鳥類が食べるためにとっておいたもの(貯食)を食べ残すことをねらっています。
とっておくために、親である植物から離れたところへ運んでいるので、それがドングリやクルミにとっての利点になります。
他にも水やアリなどにタネを運んでもらう戦略をとるものもあります。
3 越冬のためにやってきた冬鳥
落葉する冬には、鳥の姿を見つけやすくなります。年中いる鳥(留鳥)に加え、越冬のために北方からやってくる冬鳥もいます。
名前がわからなくても、その姿を追いかけて、観察してみるのもとても楽しいです。
実をくわえたり、その実を落としたり、次はどうするのかなど見ていると飽きません。
寒い日々が続き、公園や森林に行くことに二の足を踏んでいる方にとって、このような戦略を実際に見てみることは、森林浴の楽しみになるのではないでしょうか。
その他、落葉した葉も楽しめます。さまざまな色や形、そして匂いもあります。
特に日に当たって乾いた暖かな落ち葉の香りはホッとさせてくれます。

この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...
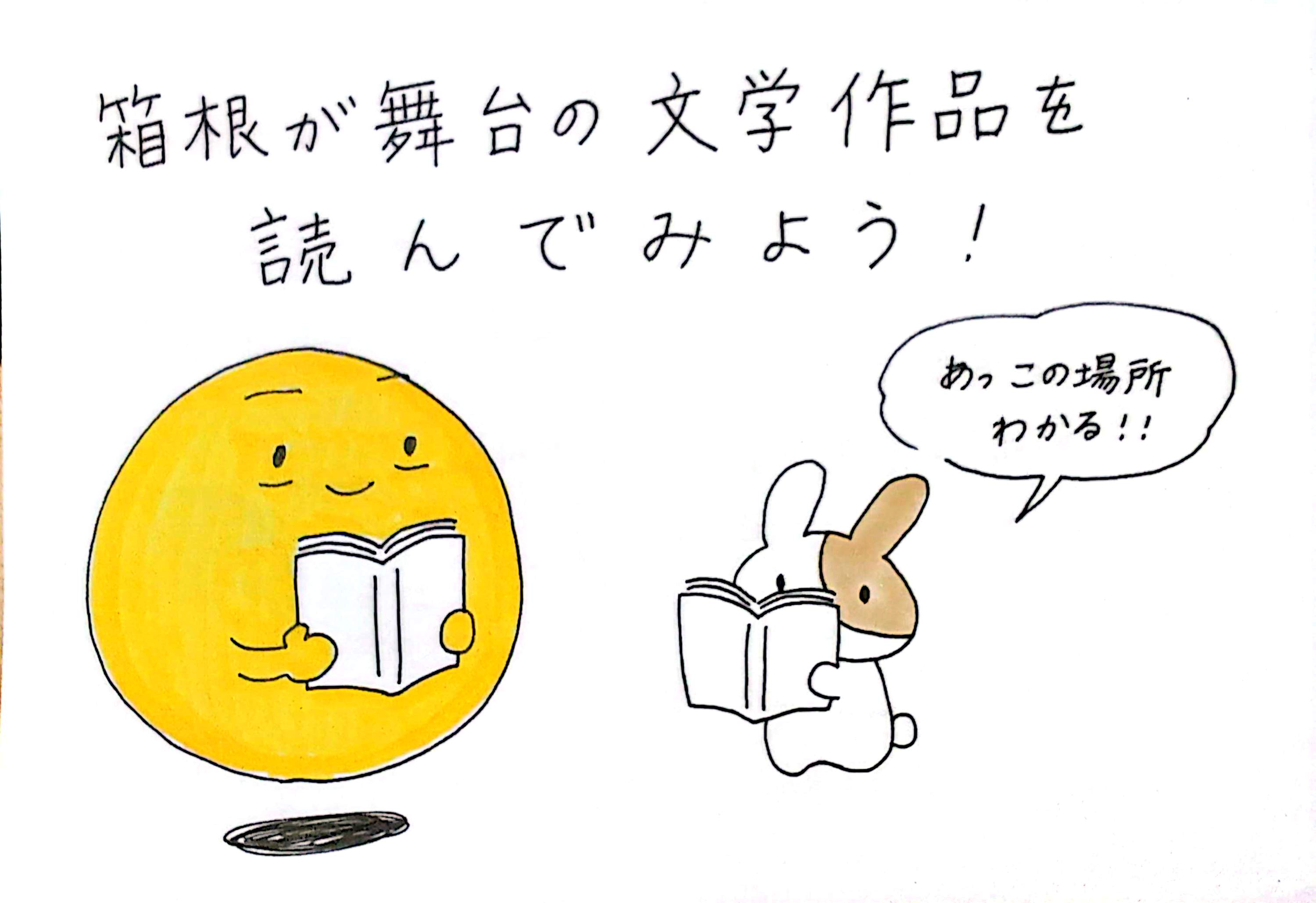
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...