
髪・肌・爪にあらわれる、女性の体の変化
最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

多くの森林には、コケやシダがいます。皆さんも多くの機会に目にしていると思います。この2種類の植物は、花が咲いたり、実がなったりするわけではありません(注)。今回はこの植物について、入門編として簡単に解説していきます。森林での楽しみがまた一つ増えるのではないでしょうか。
注:種類によっては、コケに花のようなものがある場合もありますが、これは「蒴(さく)」といい、繁殖のための花ではありません。また、コケ植物でなくても『コケ』と名前につく植物があります。
コケとシダの共通点と相違点
多くの植物は、花が咲き、実がなり、種子を作り、その種子をもとに増えていきます。これらは種子植物といいます。一方、コケとシダは種子をつくる訳ではありません。それでは何で増えていくのでしょうか。それは胞子です。
 コケとシダの共通点は、胞子で増えることと双方共に葉緑体を持ち、光合成をするということです。一方、相違点は何かというと、シダには維管束(※)があり、コケには維管束がない(さらに根もない)ということです。
コケとシダの共通点は、胞子で増えることと双方共に葉緑体を持ち、光合成をするということです。一方、相違点は何かというと、シダには維管束(※)があり、コケには維管束がない(さらに根もない)ということです。
※維管束とは根が吸収した水分を運ぶための導管(シダ植物の場合は仮導管)と、光合成でできた栄養分を運ぶための師管が束になったもの
進化の順番からいえば、いずれも起源が古く、いわゆる「下等」と呼ばれる植物です。ただ、この状態で居場所を見つけ、それぞれ多くの種類が存在しています。
それでは、コケとシダについて、順に説明していきます。
コケってなに?
もともと“コケ”という言葉は、漢字では「木毛」や「小毛」と書かれていたように、木に生える毛のようなものをまとめてコケと呼んでいたのです。
その後分類ができて、「苔」という用語になりました。
コケは、根や維管束やクチクラ層を持たない植物です。原始的な植物といえます。
コケは根がない代わりに「仮根(かこん)」と呼ばれる地面に身体を固定するための器官を持ちます。ただし、根とは異なり、水や養分を吸い上げる機能はありません。水分はどうしているかというと、からだ全体から取り入れることができるようになっています。他の植物体のようにクチクラ層などの乾燥を防ぐ器官は発達していません。また、維管束がないので、お互いに寄り添うことで体を支え合っており、かつ乾燥を防いでいます。養分は、光合成により得ています。日本には1,800種以上のコケ植物がいます。
特徴的なのは、乾燥してしまった場合に、一時的に生命活動を休止します。そして水分が得られるようになったら再び光合成などの生命活動を開始するのです。この性質を専門用語で「変水性」と呼びます。この性質があるからこそ、他の植物ではなかなか生きていくことのできない木や岩の上などでコケは暮らしていくことができるのです。
シダってなに?
日本で観察されるシダの種類は1,000種類を超え、日本はシダの宝庫となっています。前にも述べたとおり、種子ではなく胞子で繁殖し、胞子体と配偶体がそれぞれ独立している維管束植物の総称がシダ植物です。
シダは湿った場所が好きな植物です。谷筋の杉林などの暗くて湿った場所や、渓流沿いなどに多くいます。山菜として親しまれているワラビ、ゼンマイ、コゴミは、すべてシダ植物です。

シダやコケを楽しむには
時期については、シダもコケも1年中楽しむことができます。コケはコケそのものを見ることや胞子体の観察。シダについても、葉だけでなく胞子の観察も楽しめます。いずれにしろルーペ(10倍〜20倍程度)を持参されるのがいいと思います。
場所について、コケ植物は湿度があるところ。そして、木の幹、岩の上、石垣などに生えています。シダ植物も湿気があるところ、日が当たらないところに生えています。
コケ植物については、乾燥しているときと湿っている時では、姿かたちが大きく変化します。小型の霧吹きなどを持参するとその変化を楽しむことができます。
参考図書
コケはともだち 著者・藤井久子 監修・秋山弘之 リトルモア
苔の話 秋山弘之著 中公新書
改訂版コケに誘われコケ入門 著者・秋山弘之他 文一総合出版
くらべてわかるシダ 文–桶川 修 写真–大作晃一 山と渓谷社
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...
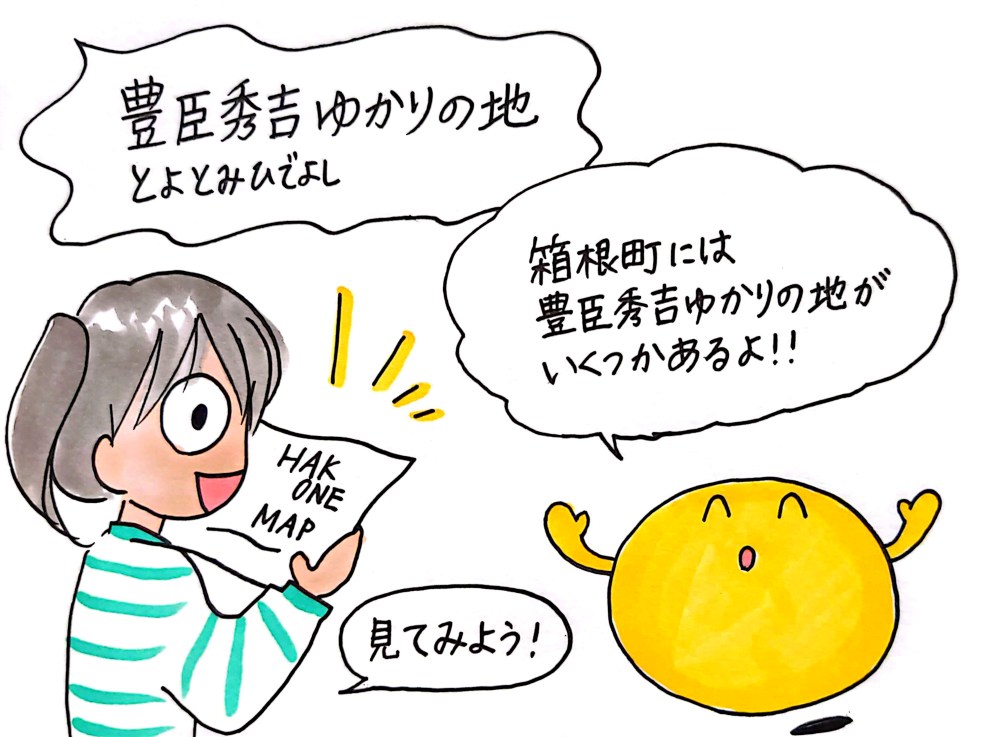
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...