
冬至を越えて、冬が深まるときの養生
冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

ちょっとした知識(4回目)は、樹木の戦略です。
花と葉は、それぞれの働きに応じて、生きていくために様々な戦略をとっています。
みなさまの暮らしの中でも何かのヒントになることもあるのではないでしょうか。
花の働きとは何でしょう。それは、昆虫を呼び寄せるための器官です。
ハチやチョウなどの昆虫に花粉を運んでもらい、受粉することによって種子をつくることができます。そのために様々な戦略をとっています。

ウメやサクラはまず、花が咲き、そして葉が伸びてきます。これは、葉が先に伸びると花が目立ちにくいので、そういう工夫をしていると考えられます。
ここで疑問が浮かびます。花が咲くためのエネルギーはどうしているのか?
樹木は光合成をすることでエネルギーを得るので、葉が出ていなければそれができません。安心してください。葉を落とす前に、エネルギーを樹木に蓄えていて、それを使うようです。
春に花が咲く樹木と夏から秋に花が咲く樹木があります。
花が咲くのは種子をつくるためです。そして種子の役割の一つに、都合の悪い環境に耐えて生き延びることがあります。
夏から秋に花が咲くのはその樹木にとって都合の悪い環境である寒い冬を種子の状態で過ごすためと考えられます。同様に春に花が咲くのは、その樹木にとって都合が悪い環境である暑い夏を種子で過ごすためです。
ウメの花が先に咲き、その次にサクラの花が咲きます。それぞれの樹木が開花する温度が違うことからそうなります。
そこには同時期に花を咲かせると媒介する昆虫に出会える確率が減る。そのために咲く時期を変える戦略をとっているのでしょう。

生物の種類によって色の見え方がそれぞれ異なっているようです。そのため、植物は来て欲しい昆虫などに合わせて、花の色を変えているとされています。
ちなみに緑色の花はありません。それは葉と同じ色では目立たないからかもしれません。
葉の働きは、光合成を行い、エネルギーを得ることです。
つまり、根から吸った水と二酸化炭素を材料として、葉(葉緑体)で光を利用して酸素を放出し、デンプンを作っています。そのために様々な戦略をとっています。

葉っぱを伸ばして光を得ようとする姿は、数多く見ることができます。葉が重ならないようにしていたり、少しでも太陽に当たるように葉を伸ばしていたり。どうやって光を得ているかを意識して樹木をみると、いろんな戦略を見つけられます。
ツバキの葉は厚く、ワックスでも塗ってあるようにコーティングされています。常緑樹のツバキの葉は、長く樹木についているので、風や乾燥に負けないようにこういった工夫をしているのです。
一方、落葉樹はそれほど厚くはありません。毎年生え変わるものなので、そうする必要はないのでしょう。
葉は、大きい方が光合成の能力が優れており、幹を太らせることができます。ホオノキ、トチノキ、キリなどがそれです。でも大きな葉からは水分の蒸散も多くなります。根から水分をしっかりと確保できる場所でなければ生育できなくなります。
森林浴にはいろんな効果があり、森林にいるだけでその効果が享受できます。少し知識があり、森林の中で何を観察するのかが見えてくると楽しみも多くなるのではないでしょうか。今回は花と葉の戦略でした。今後も実践的なものを紹介していきます。
参考図書
「樹木ハカセになろう」 石井誠治著 岩波ジュニア新書
「植物学『超』入門」田中 修著 サイエンス・アイ新書
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...
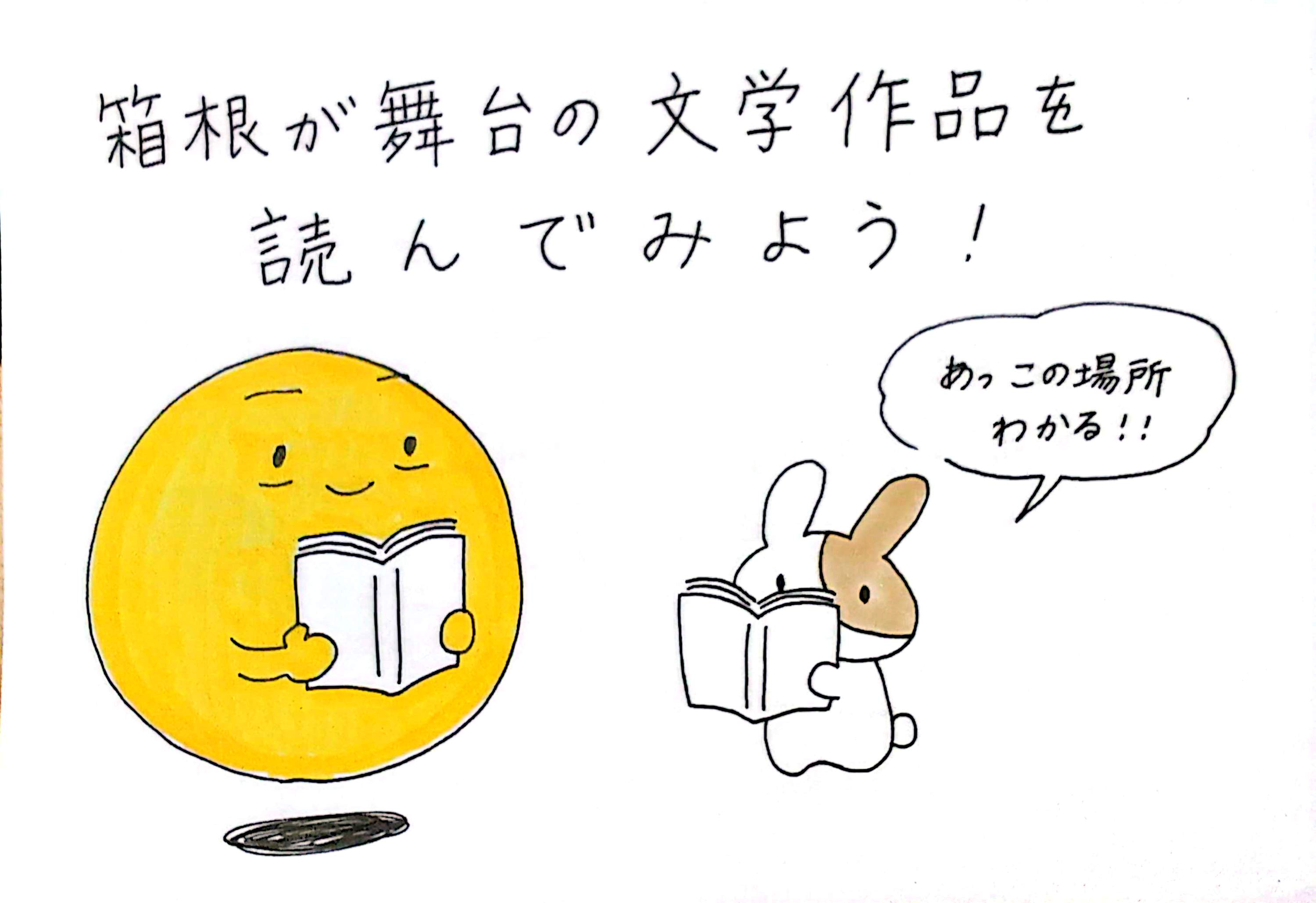
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

私たちは、人生の約3分の1を睡眠に費やしています。毎日だいたい同じ時間だけ眠っているはずなのに、ぐっすり眠れた日もあれば、まったく眠れなかったという日もあります。また、短い睡眠時間でもすっきりと起きら...
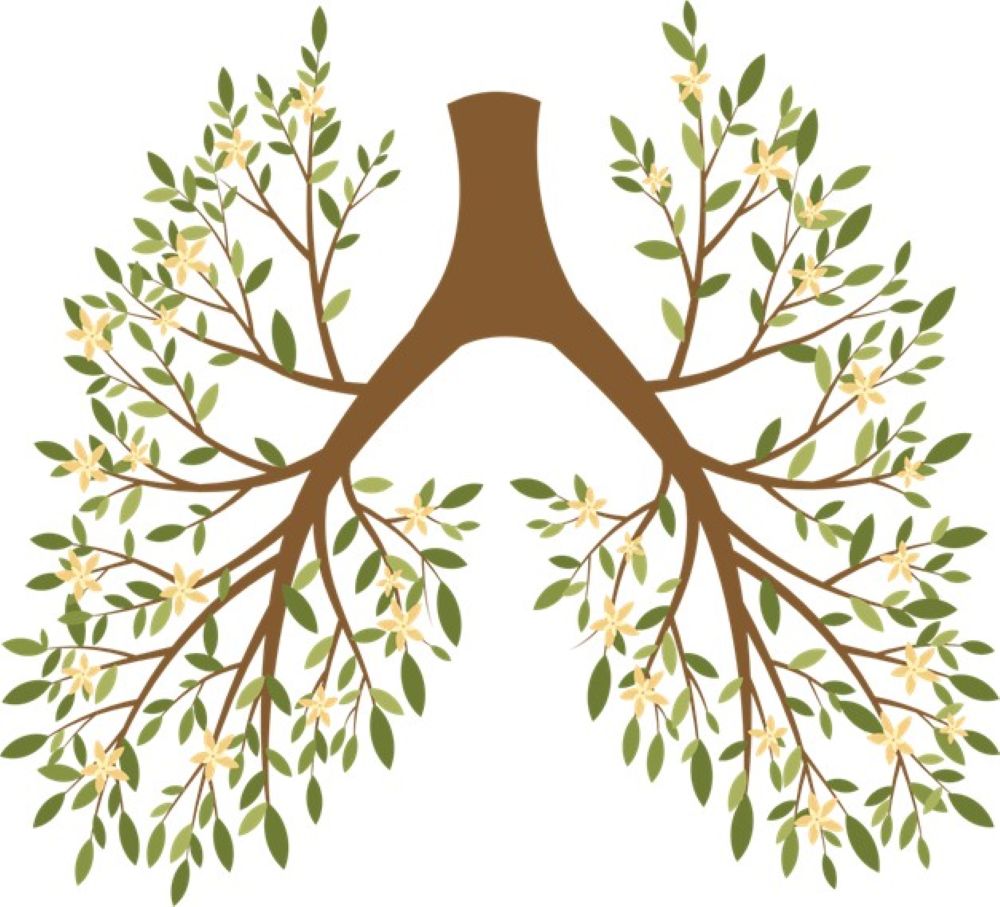
ホリスティック(Holistic)という言葉は、ギリシャ語で「全体性」を意味する「ホロス(holos)」を語源としています。 そこから派生した言葉には、whole(全体)、heal(癒す)、healt...