
皇居お濠と皇居東御苑、2月の森林浴
2026年2月14日。快晴。気温は10℃から14℃。一週間前の大雪が嘘のように、空は澄みきり、光はやわらかく、空気は透き通っていました。2月の森は、寒さの中にあるのではなく、静けさの中にあります。そし...

神奈川県横浜市北部にあり、横浜市の市民の森に指定されている寺家ふるさと村(※)にて新年早々森林浴を楽しみました。その様子をお伝えします。
※東京都町田市と川崎市に隣接し、雑木林の丘に挟まれた「谷戸田」と呼ばれる細長く伸びた水田が幾筋もある「昔ながらの横浜の田園風景」が色濃く残っているところです。
快晴。気温は6度。手袋、マフラー、帽子をして、朝のピーンとした空気を感じながらスタート。まずは寺家ふるさと村内にある熊野神社を参拝。
常緑樹の多い神社の参拝から開始
神社への急な坂道を登っていくとヒサカキがありました。神事に使われるので、神社によく植えられている樹木です。本来はサカキを用いるのですが、東日本ではサカキは自生していないので、その代わりにヒサカキを用いることが多いとのこと。3月ごろに花が咲き、その匂いは独特なものです。
ちなみにお寺ではシキミが植えられていることが多いです。仏事に用い、有毒ですが、抹香や線香にもなります。
社殿の直前にはモミの古木がありました。かなりの高さがあり、見上げると緑色の葉の間から青い空が見えてきます。風にそよぐ様子を眺めていると心が落ち着いてきました。
紹介したヒサカキやモミの木は常緑樹。神社やお寺には、常緑樹が多く植えられています。ご神木にもスギやクスノキなどの常緑樹が多いですね。
サザンカやツバキの花が咲いています
お参りを済ませ、尾根沿いの道を進んでいきます。
赤い花が咲いています。サザンカです。カンツバキの花も咲いています。その他いろんな種類の椿があり、つぼみが見られます。これから次々と咲いていくのでしょう。
葉っぱを触ってみるとすべすべしていて硬さを感じます。葉っぱから水分が蒸発しない工夫とのことです。
冬ならではの景色を楽しみます
冬は、落葉樹が葉を落とし、空気も乾燥しているので、見通しがよく遠くまで見渡すことができます。そして鳥たちも葉っぱに隠れることなく姿を見つけやすくなっています。鳥たちの鳴き声を聞きながら姿を探していくと見えてきますね。
ふと見回すと、茶色い葉をつけた樹木があります。クヌギやコナラです。本来は枝に残らないのですが、日当たりの関係か落葉に必要な葉柄の離層の形成が遅れて、残ってしまったようです。不思議さを感じますね。
下を見てみると様々な形の葉っぱが落ちていました。クヌギ、コナラ、ホオノキなどで、大きさも形も違っています。手のひらいっぱいにすくって匂いを楽しみました。
冬芽や葉痕を見てみました
歩いていると落葉樹の冬芽を見ることができます。コブシのように毛に覆われているものや、サクラなど鱗のようなものに守られているものなど様々です。それと共に、葉痕(葉っぱが木の枝から落ちた後に、枝に残る傷跡)にとても可愛らしいものがあり、それを見つけるのも楽しいです。オニグルミの葉痕は羊の顔に見えたり、クズの葉痕も人の笑顔に見えたりします。
落葉樹の枝をじっくりと眺めてみるといろいろと発見できると思います。
そして尾根を下っていくと大池に到着です。池は凍っていて、普段ではよくみることができる水鳥たちは残念ながら今日は見ることができませんでした。
寺家の田んぼの脇を抜けて歩いていくと陽のあたりがいい場所にスミレの花が咲いていました。タチツボスミレです。関東では3〜4月に咲くとされていますが、とても早いです。見つけるととても嬉しいです。
冬でも風がなく晴れていれば、手袋も不要で、歩いているととてもゆったりとした気分になることができます。森に出かけて、いろんな季節の森林浴を楽しんでみませんか。
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

2026年2月14日。快晴。気温は10℃から14℃。一週間前の大雪が嘘のように、空は澄みきり、光はやわらかく、空気は透き通っていました。2月の森は、寒さの中にあるのではなく、静けさの中にあります。そし...

森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...
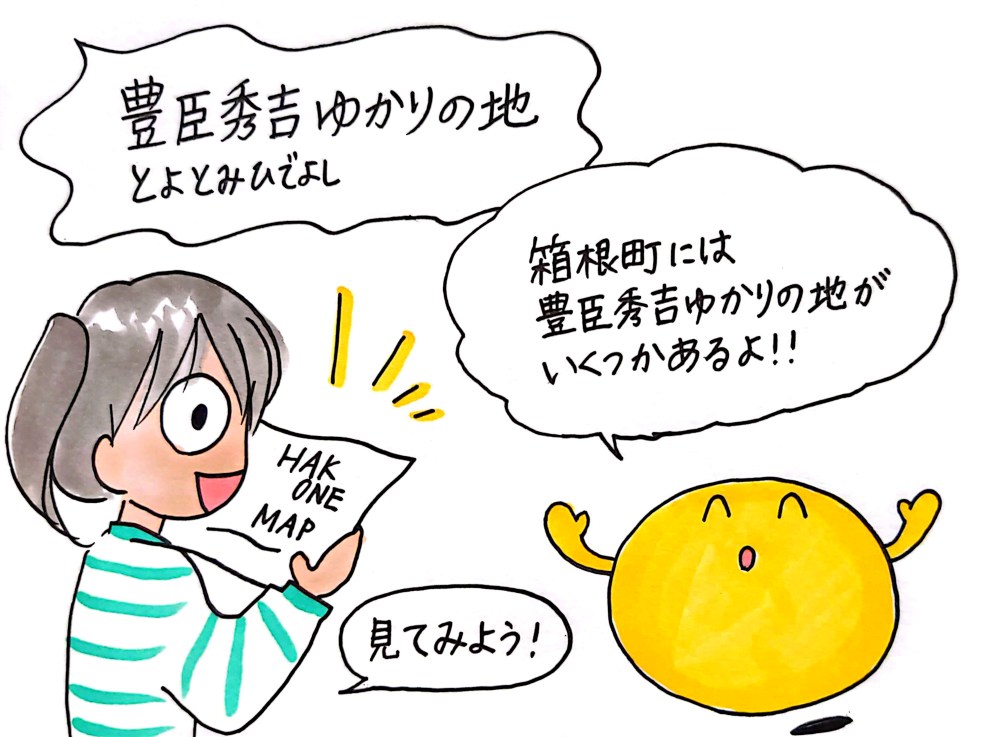
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...