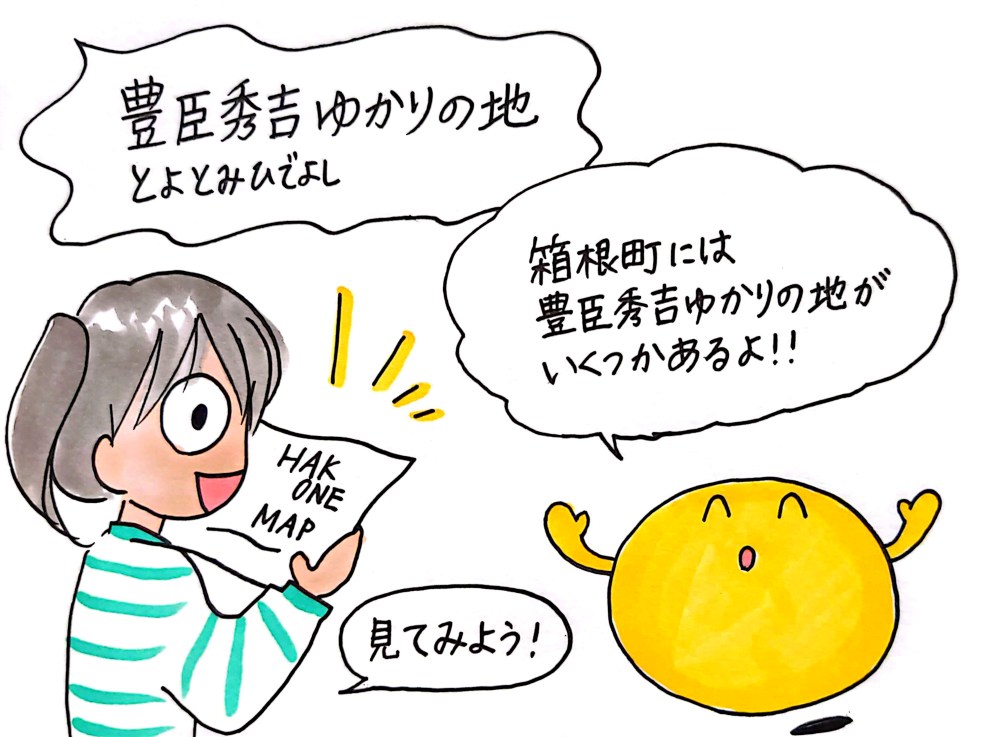
箱根町には豊臣秀吉ゆかりの地がいくつかあるよ!
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

森林浴ではいろんな変化が楽しめることを紹介してきました。
ガイドがいなくても楽しめることを伝えているのですが、「そんなこといっても、ガイドの説明がないとなかなか気づくことができません」との話をよく聞きます。
そこで、変化を見つける手がかりになる、植物や森林の生態に関する知識とそれを生かした森林浴の楽しみ方を今回紹介します。
植物は、動物や昆虫とは異なり、何かを食べなくても成長することができます。
そうです光合成を行いながら成長するのです。光合成に必要なのは光と二酸化炭素と水です。
これらを取り入れることによって、自分だけではなく、すべての生物のエネルギーのもととなる養分(デンプンなど)と酸素を合成しています。
人間だけではなくすべての動物は植物を食べて生きています。
肉食動物もいるのでそれは違うのではないかと思われる方もいるかもしれません。
でも肉食動物が食べる動物も草を食べて成長するものが多いなど、もとをたどれば植物から得られる養分を食べていることになります。
なので、森林浴を楽しむ際に、森林内の樹木や草、コケなどの植物には敬意を払って接しましょう。
森林内には、他にも、菌類、土壌微生物、昆虫、鳥、は虫類、ほ乳類など様々な生き物の生息・生育の場となっており、生態系の維持には配慮が必要です。
エネルギーのもとを合成する「光合成」は、植物の中の葉緑体で行われます。多くは葉にありますが、枝や幹でも葉緑体のあるところ(緑色のところ)では行われています。
葉は太陽光を求めて、他の葉と重ならないように伸びていきます。
枝を伸ばしてその先に葉を出すものや、互い違いに葉を出すなど、他の葉の影にならないようにいろいろな工夫をしています。
樹木には、落葉樹と常緑樹があります。
落葉樹は、「秋の末になると葉が落ち、春になるとまた新しい葉を生ずる樹木」のことで、それ以外の「一年を通して常に葉がある樹木」が常緑樹です。そして、どちらの樹木の葉も生え変わります。
新葉と古い葉は同じ緑でも色が異なります。また、新葉は古い葉よりも柔らかいです。
意識して視覚(緑の違いをみる)や触覚(葉を触ってみる)を使って楽しんでみましょう。
落葉樹は、春に一斉に生え変わります。
では常緑樹はどのようになっているのでしょうか。
同じ葉が長期間付いているわけではなく、1~数年ほどかけて落葉し、少しずつ生え変わります。
新葉の展開に伴って、古い葉は落ちていきます。その時期・方法は樹種によってさまざまです。
たとえば、クスノキやシラカシは4〜5月のうちの1週間くらいですべての葉を落とし、新旧の葉が交代します。
ツバキなど他の多くの常緑広葉樹の葉は、4月から6月にかけて新葉が出始めると、それと交代に古い葉が落ちます。
タブノキは完全に新旧が入れ替わるのではなくて、2~3年生の古い葉から落ちていきます。
針葉樹は10月から12月にかけて、葉の古いものから順次落ちていきます。

常緑樹でも落葉を楽しむことができます。
落ちている葉の手触りやにおいを楽しむのは、秋と冬だけではありません。
それから、常緑樹の葉は落葉樹より分厚くなっています。
それは冬の寒さや乾燥を耐えられるようにしているからとのことです。
常緑樹と落葉樹の手触りの違いも楽しめますね。
植物の一生は、花が咲き、実がなり、その中に種があります。
種は、風や、鳥や虫に運ばれて、それが発芽して次代につないでいます。
これは樹木や草などの植物に共通しています。

樹木の花は、ウメやサクラは目立つのだけれども、他の樹木の花には目立たないものがたくさんあります。
また、いつ咲くのかは樹木の戦略によるので、花が咲いてから葉を出すもの、葉を出してから花が咲くものなどさまざまです。
でも植物の一生は共通しているので、「この樹木の花はどうなっているのだろう」、「この間、花が咲いていたけれども実はどうなっているのだろうか」「種はどんな形になっているのだろうか」など、観察の手がかりになります。
写真は、カキ(柿)の花とクスノキの花です。見たことがない方が多いのではないでしょうか。
どうでしょう。ちょっとした知識で、森林浴が楽しくなる気がしてきたでしょうか。次回もこの続きを紹介していきます。
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。
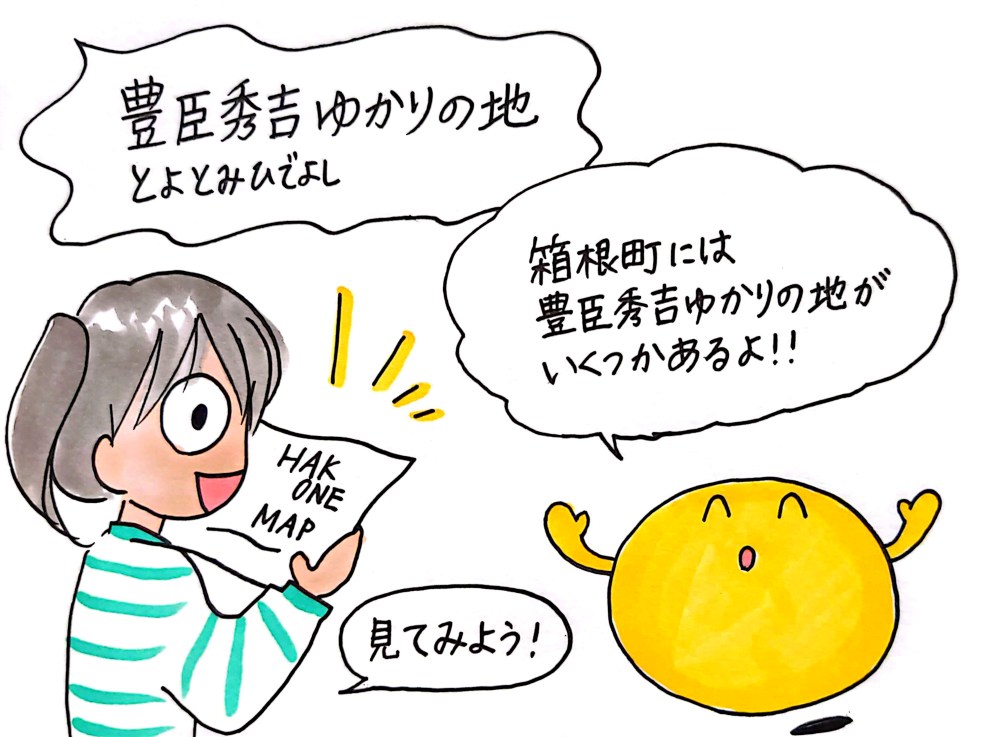
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...