
冬至を越えて、冬が深まるときの養生
冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

今や地球上の人口が80億人を超えた、とされていて100億人を超えるのももうすぐと言われています。
この先食料問題がさらに過酷になっていくので、フードロスも含めて、自分たちの食に関する問題がひと事ではなくなってきています。
縄文時代の人口については、正確な数字は不明ですが、日本の中でおよそ数十万人から数百万人程度と推定されています。
当時の日本列島には、複数の地域社会が形成され、それぞれに異なる文化が育まれていました。
ただし、当時は人口増加が緩やかだったため、広大な土地に比べて人口密度は低く、また、狩猟採集生活を営んでいたため、人口密集地域という概念は存在しませんでした。
縄文時代後期には、農耕や畜産が始まり、定住生活が広がったことから、人口も増加していったとされています。
しかし、大陸から鉄器が伝わり農耕文化の発展に伴い、縄文時代の豊かな自然環境も次第に破壊されていきました。
それが1万年守られてきた自然環境維持が、現代の自然環境破壊にもつながるきっかけではないかと思います。
この縄文時代は、その名前が示すように、土器や繊維などに特徴的な縄目模様があしらわれた美しい陶器文化が栄え、また、彫刻や土偶、石造物、土塁などの独特の文化遺産も残されました。
縄文時代は、当時の地球温暖化の影響によって、気候が穏やかであり、多様な生物が豊富に存在していたことが特徴でした。また、海岸線の変動や火山活動などもあり、人々は自然と共存しながら生活していました。

縄文時代には、狩猟採集民族であった人々が、発酵や加熱調理などの食品加工技術を独自に発展させ、文化の豊かさを示しています。
また、縄文時代の社会は、女性が重要な役割を果たしていたことが知られており、母系社会の特徴も見られます。
発酵は、縄文時代から日本で行われていたと考えられています。当時の人々は、魚やイモ類などの食品を発酵させて保存し、食糧不足に備えたとされています。
また、森の中で採れる木の実や果物を発酵させた酒も、儀式や祭りの際に飲まれていたとされています。
縄文時代には、土器や石器を使った加熱調理が行われていたことも知られていますが、発酵も重要な食品加工技術であったと考えられています。
食料が豊富に取れない、季節に左右される時代だからこそ人々は明日を生き抜くための知恵として、発酵のテクニックを生かして食料を保存する術を生活に取り入れていたのです。

日本人は、いつ頃から納豆を食べていたのか想像したことありますか?
それは歴史の謎ですが、中国大陸から稲の栽培方法が伝わる縄文時代の終わり頃には、すでに納豆のような食べ物はあったという説もあります。
現在、私たちが日常的に食べている<納豆>という認識も、あだ名もまだなかったと思われますが、縄文人はネバネバと糸を引く奇妙な豆を食べていた可能性が高いのです。
縄文時代の主食は栗やトチ、くるみ、どんぐりなどのナッツ系とアワやひえといった雑穀、そして山芋や長芋、里芋などの芋類とみられています。
その他の魚類や山菜、キノコなどの利用も含めて、摂取カロリーを計算すると1日の食料の80%は植物系からとっていました。
現代の時代で言うとほぼベジタリアン、プラントベースの食事だったのでしょう。
この頃は魚、肉などはたまにとれるご馳走でしたので、保存方法として塩漬けなどにして少しでも長く食べられる工夫をしていました。
山芋のとろろ汁と同じように、ねばねばが旨味になっているのが、大豆発酵食品の納豆です。
山芋をすりおろして生で食べるような経験を身につけていた縄文人にとって、糸を引く豆も、それほど抵抗なく食べることができたのは間違いありません。
そして米の後を追うように、大豆が縄文時代の終わり頃に、中国大陸から渡ってきたようです。
日本産の稲藁1本には、ほぼ1000万個の納豆菌が、胞子の状態で付着しており、藁を束ねて藁苞(わらつと)、と言う容器を作り、その中に煮豆を詰めておけば、煮豆からネバネバと糸を引く可能性が高くなるのです。
苞(つと)というと、いまでは納豆容器のイメージが強いのですが、食べものを入れる万能の容器として、日常的に使用されていました。
納豆菌は学名を<バチルス、ナットウ>と言い、枯草菌の1種ですから、枯草菌はもちろん、土の中や稲の切り株、空気中と、日本中どこでも生息しています。
縄文人の住居は竪穴式住居ですから、一種の発酵室のような性格もあり、しかも
稲藁を敷いて生活していましたから、納豆出現の可能性は極めて高かったわけです。
一度発酵させた納豆は乾燥させたりすると保存や消化にも優れているのと、納豆菌は栄養もあるので縄文人は重要な栄養源としていたのでしょう。

縄文時代の食生活や発酵の取り入れ方、自然環境との関わり方。
この時代は自然と発酵と人間がバランスよく均衡が取れていたので、人間の歴史の中でも長く続いたサステナブルな時代でした。
森林伐採やゴミ問題、温暖化など、明らかに戦後70年くらいの間に凄まじい勢いで近代化が進んでいる世の中で、さまざまな問題が起きています。
便利な時代で、なんでもいつでも手に入る時代だから、忘れていることが多いですね。私たちの子供時代と今でも明らかに地球環境が変わってきています。
毎年、巨大台風が増えたり、農作物や回遊する魚の種類が変わったり、このままいくと人間が暮らせない惑星になってしまうかもですね。
発酵食品に目を向けても環境が変わって農作物や、食材が取れなくなったり温度が変わって発酵の仕込みの工程に必要な温度帯が変わってしまったりして、作れなくなってきているものも多く出てきています。
一人一人が100年、1000年先の子孫のことを考えて次の時代にバトンを渡すべく、この地球上の自然環境を守っていくことを意識していくことが大切ですね。
発酵の世界は菌の世界。
菌が教えてくれる人間と自然との共存は、地球からのメッセージなのです。
まずは、身の回りのスーパーで買えるもの、フードロス、ゴミの削減、買いすぎない、など意識することが必須ですね。
あなたが地球のために、100年後の未来のために今日からできること、なんですか?
この記事を書いた人

山田 雅恵(やまだ まさえ)
旅する発酵料理家・ファッションデザイナー
旅と発酵の世界をこよなく愛し、発酵の醸し出す世界を広めるために日本各地、海外にて発酵を求め活動している。
文化女子大学家政学部服装学科卒業後、エスモードパリ本校にて学ぶ。ニースのコンクールにてクリエーション賞受賞。パリコレなどのフィッターを経験。帰国後にインディーズブランド立ち上げ、セレクトショップ、大手アパレルブランド数社のデザイナー、京都にて京友禅の着物作りを経て、デザイン企画会社を仲間と起業。
ファッションデザイナーでありながら、天然酵母のパンの発酵と自然の世界に魅せられ、発酵の世界へ。日本の麹の天才調味料、醤(ひしお)仕込み、活用の仕方を広げるべく、日本全国、フランスでも仕込み会を開催。衣食住・心を、発酵を通して、世の中良くしたいという思いで、神奈川県の鶴巻温泉をベースにして、日本全国で活動中。
未来の子供を食で学ぶキッズサイエンス、子供のものづくりの能力を引き出すアートクラスも各地で開催。古民家再生プロジェクトにも関わる。
2018年度より【お裁縫くらす】を日本各地で開催。お裁縫がある暮らしを提案すべく、使える日常雑貨などを作り、自分で愛着のものを作り身につけることを伝えることを使命として、活動中です。
「旅する発酵倶楽部」:https://yamadamasae.com/

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...
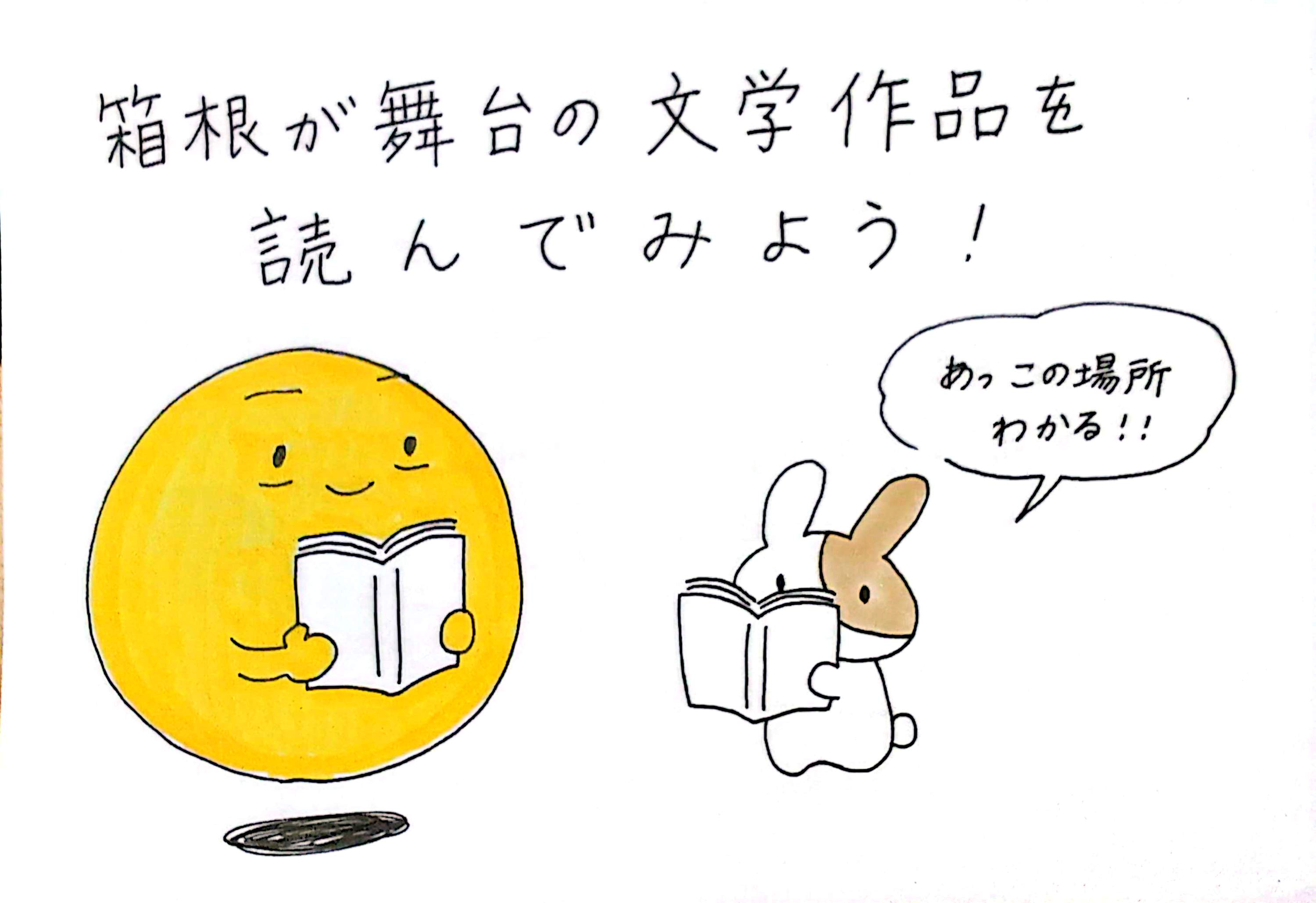
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

私たちは、人生の約3分の1を睡眠に費やしています。毎日だいたい同じ時間だけ眠っているはずなのに、ぐっすり眠れた日もあれば、まったく眠れなかったという日もあります。また、短い睡眠時間でもすっきりと起きら...
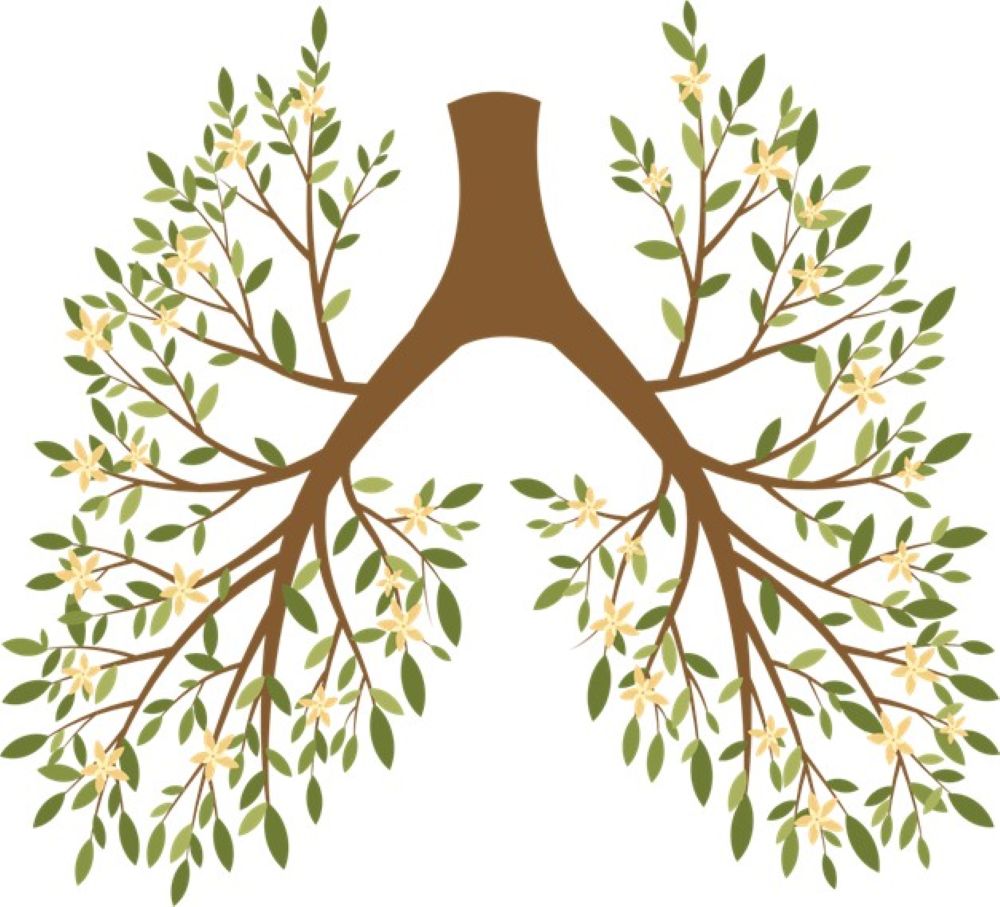
ホリスティック(Holistic)という言葉は、ギリシャ語で「全体性」を意味する「ホロス(holos)」を語源としています。 そこから派生した言葉には、whole(全体)、heal(癒す)、healt...