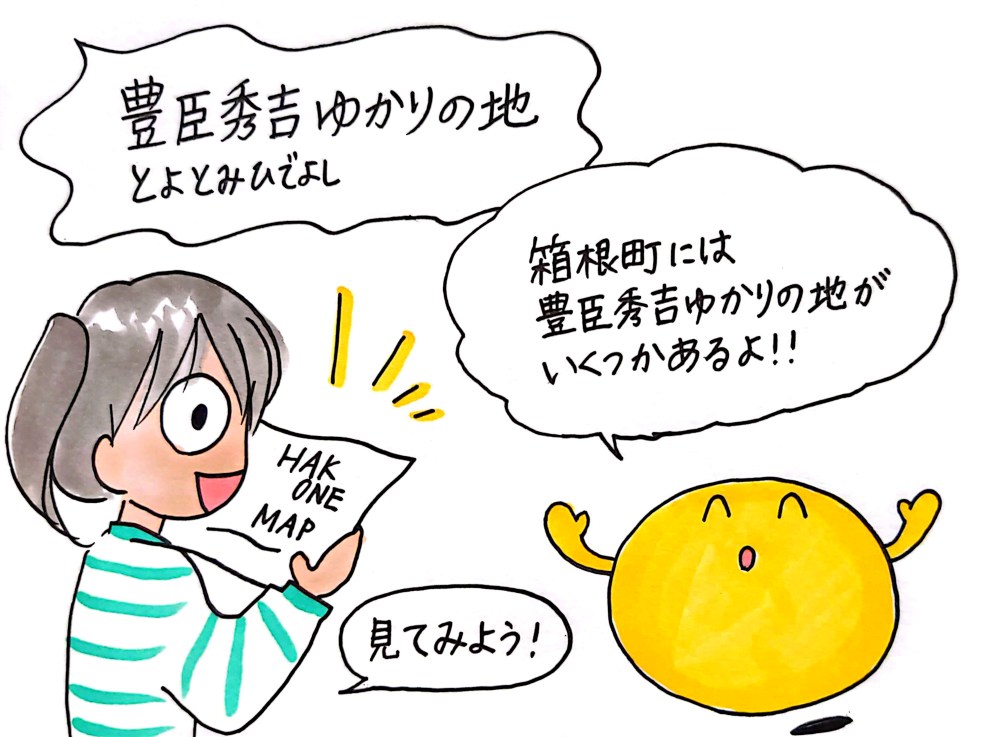
箱根町には豊臣秀吉ゆかりの地がいくつかあるよ!
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

桜の花が咲き、落葉樹は様々な芽吹きが目立ってきました。これからの季節、落葉樹は日々その姿を変えていきます。
一方、冬も葉をつけている常緑樹はどうなのでしょうか。今回は常緑樹の葉と花に焦点を当ててみました。そこにはいろんな戦略があります。
お寺や神社には、クスノキ、スダジイ、スギなどの常緑樹が多く植えられています。それは冬にも葉を落とさずに緑のままでいる姿を「永遠の命」の象徴として神木や霊木として崇めていたからです。

常緑樹はその名の通り「緑の葉が常にある」樹木ですが、その葉はずーっとあるわけではなく、生え変わります。
生え変わる時期や既にある葉がどのぐらいの期間で落ちるのかは樹種により異なります。
写真のキンモクセイの葉に、少し色が変わった小さな葉が見えます。これは新芽から展開した葉です。
春は多くの常緑樹の若葉を見ることができます。

4月のクスノキには、オレンジから赤色の葉と緑の葉の2種類を一つの樹木に見ることができます。オレンジから赤色の葉は、このあとに落葉します。黄緑色の葉は今年芽吹いたもので、これから1年間葉として働くものです。このようにして、クスノキは4月に一斉に生え変わります。葉の寿命は1年のため、常緑樹の中でクスノキの葉はあまり丈夫にできていません。そのおかげで光合成の効率が高く、巨木が多くなっています。
他の常緑樹の葉は、落葉樹のように毎年生え変わるわけではありません。
常緑樹と落葉樹共通ですが、花には虫媒花と風媒花があります。虫媒花は「虫を使って花粉を運ぶ花」です。一方、風媒花は、「風を使って花粉を運ぶ花」です。
虫媒花は、虫に来てもらう必要があります。そのために虫に目立つ姿になるように工夫し、色も来て欲しい虫が気付きやすいものにしています。さらに同じ種類の樹木でも雄花と雌花では、より雄花が派手にできています。それは虫が先に雄花に来て、そこで花粉を体につけて雌花に移ってその花粉をつけて欲しいからです。

写真はアオキの雌花と雄花を並べています。アオキは雌雄異株なので、雄花は雄株、雌花は雌株に咲いています。どちらが雄株なのかはわかりますよね。
そして、タブノキの花は両性花です。おしべとめしべが一つの花に同居しています。いずれも4月に花が咲きます。

針葉樹であるマツ、スギ、ヒノキは風媒花です。もともとこれらの針葉樹が生まれたときには、虫がいなかったようです。
そのため、虫ではなく、風に花粉を運んでもらう戦略を選んでいるのです。
なので、花は目立ちません。
写真はマツの雄花と雌花です。雌花は長い枝(長枝)の先端部分、雄花は長い枝の下部にあります。雄花の下にあるのは、昨年の雌花から誕生した松ぼっくりです。
ちなみに先ほど登場したキンモクセイですが、その花は、その特徴的な匂いとともに皆さん馴染みがあると思います。
ところで実は見たことがありますか。通常花の機能は昆虫を呼び寄せ、受粉することによって種子を作ることです。
そのために必要なのは実です。実の中に種子ができるのが普通です。日本にあるキンモクセイはすべて雄株なので、実をつけることができません。
どうしてそのようなものになっているのでしょうか。キンモクセイは、日本には自生していなく、中国から輸入したものです。
その際、より花の綺麗なキンモクセイの雄株を導入し、それを挿し木という方法で増やしていったのです。その結果、日本のキンモクセイは雄株だけとなり、実がならないのです。
森林浴には、ストレスホルモンの減少、血圧を正常化、免疫能の活性化などさまざまな癒し効果があることがわかっています。樹木は、いろんな戦略をとっています。そんな工夫を楽しむことで、森林浴に費やす時間が増えるのではないでしょうか。
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。
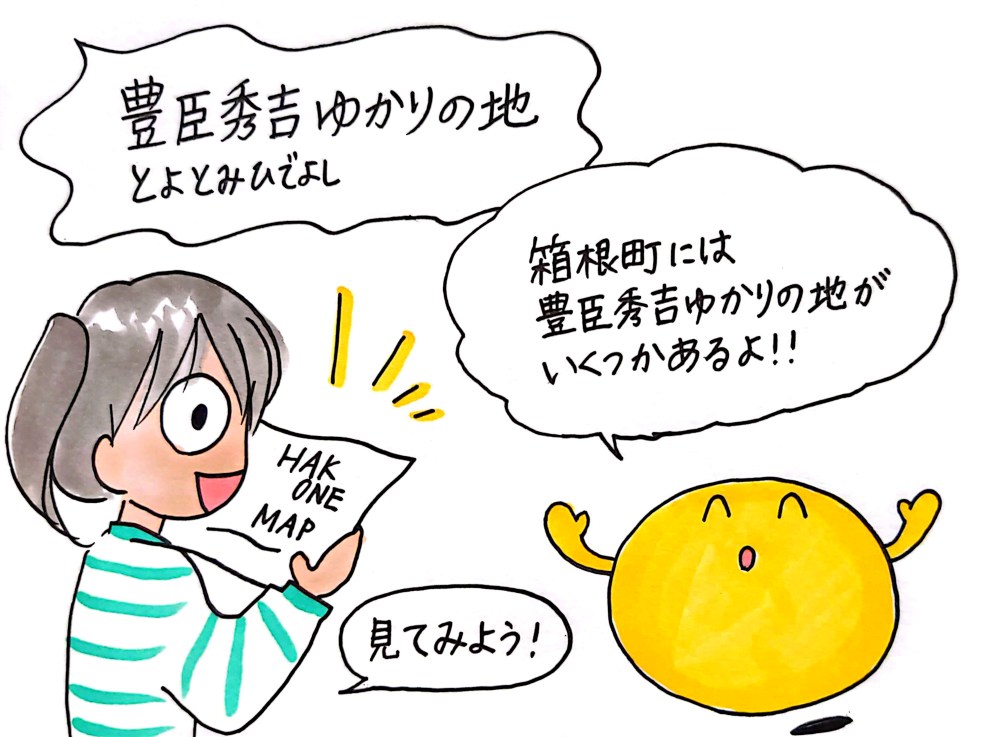
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...