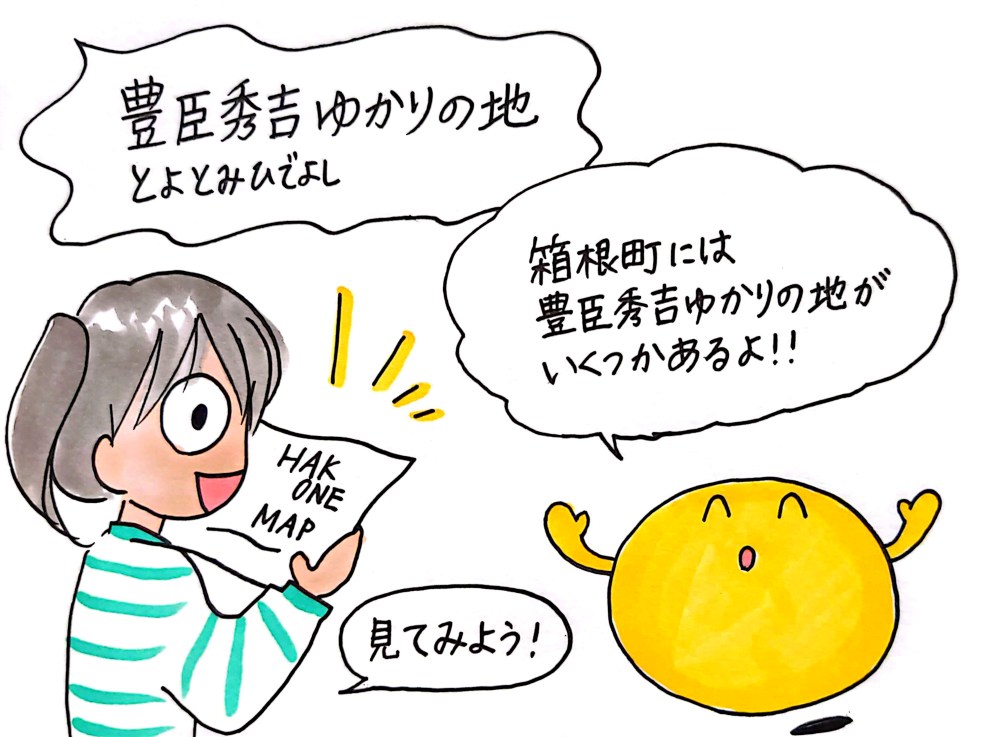
箱根町には豊臣秀吉ゆかりの地がいくつかあるよ!
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...
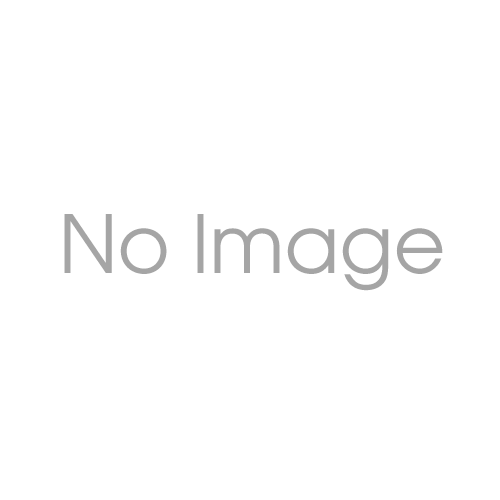
人間が手を入れない森の生態はどんな森の景色やバランスがあると思いますか?
先日8000年の手付かずの森、秋田、青森にまたがる世界遺産白神山地へ行ってきまし
た。
そこでは人生や森から学ぶこと、発酵の世界と自然のバランスなど深く感じる機会となりま
した。
8000年前というと日本では縄文時代にあたります。
昨今、三内丸山遺跡の世界遺産認定など、1万年続いた縄文時代の人々の暮らしから学ぶという話題などが多いですね。
今回はそんな白神山地から学ぶ発酵のヒントを見ていきましょう。
8000年の間、人間が手を入れない森、というのはどんな景色なのでしょう?
先人の感じ見てきた、太古の原生のブナの森が広がる、世界遺産白神山地。
縄文時代の人はこの風景を見ていたのでしょう。
自然のあるがままの世代交代とはこういうことかということを、教えてくれる景色が広がりま
す。
森に入ると大きな大木が倒れたままになりその倒木から、次の木が生えていたり。
小川が湧き出て源流のように流れていたり。
自然の仕組みと、生存競争、バランスを保って自然と共存、自分自身の役割や、世代交代など人類が学ぶことがそこにありました。
大きい樹木が倒れると、空の空間はぽっかりと大きな穴が空いたようになり、光が地面に差し込むようになります。薄暗い森の中に光が差すのです。
そうすると、次にスタンバイしていた脇に生えていた小さな木が光を生かして成長を始めます。
木のタネは一度タネが落ちた場所から芽が出て、自分で動くことができません。
与えられた環境でどう生き残っていくのか、どう成長するかそれぞれの環境が違うので、様々な木の形、大きさになっていくのです。
それには光が必要。
また地面は腐葉土の土ばかりではなく、大きな岩がゴロゴロと転がっている場所もあります。
そんな場所では大きな岩の上に木が乗っかり、根っこが包むような木の形になって成長していきます。
2本、3本が一緒になったような樹木もあったり、輪っかのように曲がっている幹の形の樹形もあったり。その形を見ると、木が辿ってきた成長の歴史がわかります。
白神山地のブナたちは曲がっていたり、同じ形の木がひとつとしてありません。
それぞれの木の形に個性があり、木と木の間隔もちょうどいい距離をそれぞれが保っているのです。
なんだか人間も同じですね。
そして、それぞれの木の距離も誰に教えられたわけではないのに、風になびいた時に木と木ががぶつかり合わないちょうどいい距離なのです。
タネが落ちて小さな苗木にはなるけども、大きく成長できずそのまま小さい木のままのものもあります。
そこからあなたは何を感じますか?
まるでスポンジ?!良質な腐葉土が作られる
日本には多くの山がありますが、私たちが多く見る山の景色は人間が植林として植えてきた山の景色がほとんどです。
ですが、白神山地はそのほとんどの地域が人間が手を加えることのない原生のブナの森が残っています。
広葉樹が多いブナの森は地面のほとんどが腐葉土で覆われております。
落ち葉が多く堆積した地面は葉っぱが重なり合い、スポンジのように生物が分解してふかふかの土へ戻っていきます。
この腐葉土が落ち葉から土になるまでは微生物による発酵、有機物から無機物への分解の流れを経て土へと戻っていきます。それが栄養のある土となるのです。
一方植林として植えられる杉などはだいたい針葉樹なので、落ち葉が少ないので腐葉土も少ない土、土壌になります。

白神山地を案内してくれたツアーガイド協会長の方が、見せてくれた腐葉土のブロック。その厚さがだいたい10 cmほどあり、手で押すとジワリとスポンジのような弾力があり断面から水が染み出してきました。
こんな腐葉土がたくさんこの白神山地の地面には積もっていて、4 M ほど積もる冬の雪どけ水や、雨などを保水してくれる働きもあります。

この記事を書いた人

山田 雅恵(やまだ まさえ)
旅する発酵料理家・ファッションデザイナー
旅と発酵の世界をこよなく愛し、発酵の醸し出す世界を広めるために日本各地、海外にて発酵を求め活動している。
文化女子大学家政学部服装学科卒業後、エスモードパリ本校にて学ぶ。ニースのコンクールにてクリエーション賞受賞。パリコレなどのフィッターを経験。帰国後にインディーズブランド立ち上げ、セレクトショップ、大手アパレルブランド数社のデザイナー、京都にて京友禅の着物作りを経て、デザイン企画会社を仲間と起業。
ファッションデザイナーでありながら、天然酵母のパンの発酵と自然の世界に魅せられ、発酵の世界へ。日本の麹の天才調味料、醤(ひしお)仕込み、活用の仕方を広げるべく、日本全国、フランスでも仕込み会を開催。衣食住・心を、発酵を通して、世の中良くしたいという思いで、神奈川県の鶴巻温泉をベースにして、日本全国で活動中。
未来の子供を食で学ぶキッズサイエンス、子供のものづくりの能力を引き出すアートクラスも各地で開催。古民家再生プロジェクトにも関わる。
2018年度より【お裁縫くらす】を日本各地で開催。お裁縫がある暮らしを提案すべく、使える日常雑貨などを作り、自分で愛着のものを作り身につけることを伝えることを使命として、活動中です。
「旅する発酵倶楽部」:https://yamadamasae.com/
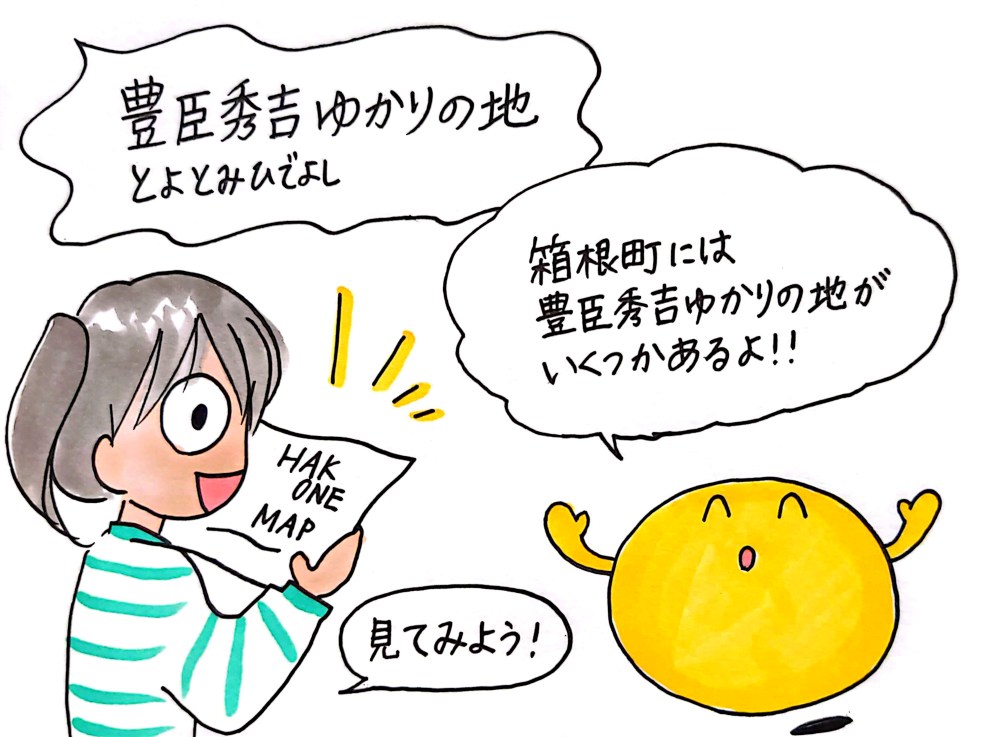
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...