
髪・肌・爪にあらわれる、女性の体の変化
最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

1都3県の緊急事態宣言が解除された3月下旬、若葉の芽吹きとサクラがきれいな弘法山公園(神奈川県秦野市)へ行ってきました。
2020年4月21日付で「はだの表丹沢森林セラピー基地」「森林セラピーロード」が認定されました。
ここ弘法山公園は、認定された5つの森林セラピーロードのうちの一つです。
今回歩いたのは、弘法山公園・吾妻山コースで、秦野駅(標高97メートル)から浅間山、弘法山(標高235メートル)、吾妻山の3つの山を経由して、鶴巻温泉駅に至る道です。
7.5km、コースタイムは2時間10分との表示があります。
マスク着用、マイボトルにお茶を入れ、昼食とおやつ持参で秦野駅をスタート。駅から数分のところにある「弘法の清水」でまずは喉を潤しました。
秦野市内には、湧水が多く見られ、その水は古代から人々の暮らしに利用されてきたそうです。
この秦野盆地湧水群が環境庁により「名水100選」に選定されています。

そして、水無川沿いを15分程度歩き、弘法山公園入口に到着。ここからは急坂。ふとスミレの花が咲いているのに気がつきました。
「他にもきっと花が咲いているはず」とあたりを見回すと、ノイバラやクサイチゴの白い花も。
何の意識もなく通り過ぎていたら見つけられなかったなと思いました。
ここからは標高差100メートルを一気に登るかなりの急坂。心拍数があがります。心持ちゆっくりと小股で歩きました。
途中、イヌシデの雄花が落ちていました。見上げるとイヌシデの若葉と雄花があります。
ただ、あたりに生えているイヌシデすべてが同じような状況ではありません。
同じイヌシデなのに、若葉の芽吹き具合はさまざまです。どうしてなのかなあと考えていると浅間山山頂(標高196メートル)に到着。
眺めもよく、ここで持参した昼食(おにぎり)タイムです。
その後は、尾根沿いの道になります。少しの勾配のみで高低差も少なく、樹木の手触りを楽しんだり、木々の様子を見たりすることができました。
おっとあぶない。樹木の根に思わず足をとられそうになりました。まわりばかりみていないで、足元にも注意しないといけませんね。

開けた場所に来ました。一面サクラです。淡いピンクの中に白い花が目立ちます。そうオオシマザクラです。
オオシマザクラの花の匂いを嗅ぐと桜餅の香りがしてきました。ソメイヨシノよりも強い香りです。ちなみに桜餅に使われるサクラの葉の塩漬けはオオシマザクラの葉を使うのが一般的です。
ちなみに、秦野市は、食用の八重桜の出荷量が全国シェア7割以上です。約130軒の農家が2500本の八重桜から特産の「桜漬け」を加工しています。

ガマズミの葉はふわふわとした触感、今の時期ならではですね。他にも芽吹いたばかりの葉のやわらかさにはびっくりしました。
キブシの花、イヌシデの花、赤くてかわいらしいイロハカエデの花、そしてヤマブキの花は、その名のとおりきれいなヤマブキ色でした。

権現山(標高243メートル)に到着。今回のコースの中では最高点。展望台があり、大山や丹沢の山々が見られ、今日は見えませんでしたが富士山も見えるところです。
相模湾や初島なども見ることができました。
このエリアは千畳敷ともいわれる開放的な平地です。満開のサクラがとてもきれいです。
ここから弘法山までは、サクラを見続けることができます。他の若葉の黄緑色と共にきれいな景色を楽しみました。
時々振り返ると日光の当たり方の違いもあり、今まで通ってきた道の違った魅力を感じることができました。
弘法山に到着。ここでまた一休み、持参した味噌ピーナッツを食べました。
秦野市は落花生の生産量が神奈川県で第一位。その落花生を用いた数々の加工品が秦野にはあります。

弘法山を抜けるとサクラの花々はなくなり、コナラ、クヌギ、シダといったいわゆる関東の雑木林になります。
樹皮を触って楽しみながら、若葉の合間からの景色を楽しみます。ときおりツピーツピーツピーという鳥の鳴き声が聞こえます。
そう、シジュウカラです。他にもヒヨドリなどのさまざまな鳥の鳴き声が聞こえます。
どの鳥の鳴き声なのかがわかるようになるともっと楽しいのになあと思いながら歩き続けます。
コースの後半は下りです。時折急な坂があり、足元に気をつけながら進みます。登ってくる方や、急いでいる方がいて、道を譲ったり、譲られたりでした。
コースの終点である鶴巻温泉駅前には、手湯があり、源泉かけ流しの温泉に手をつけることができます。とても心地よいものでした。
ゆっくり休みながら歩いたからか、コースタイムの約2倍にあたる4時間が経過していました。
その土地の地形や産物を楽しみながら行う森林浴はとてもいいものでした。
この記事を書いた人

高田裕司(たかだゆうじ)
中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター
親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...
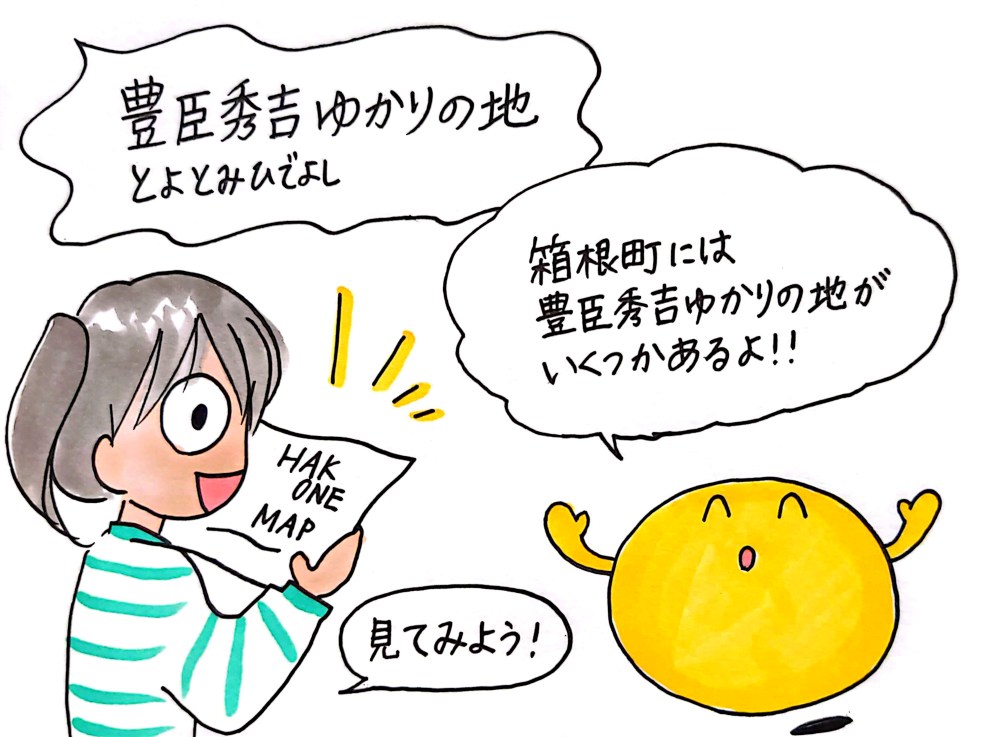
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...