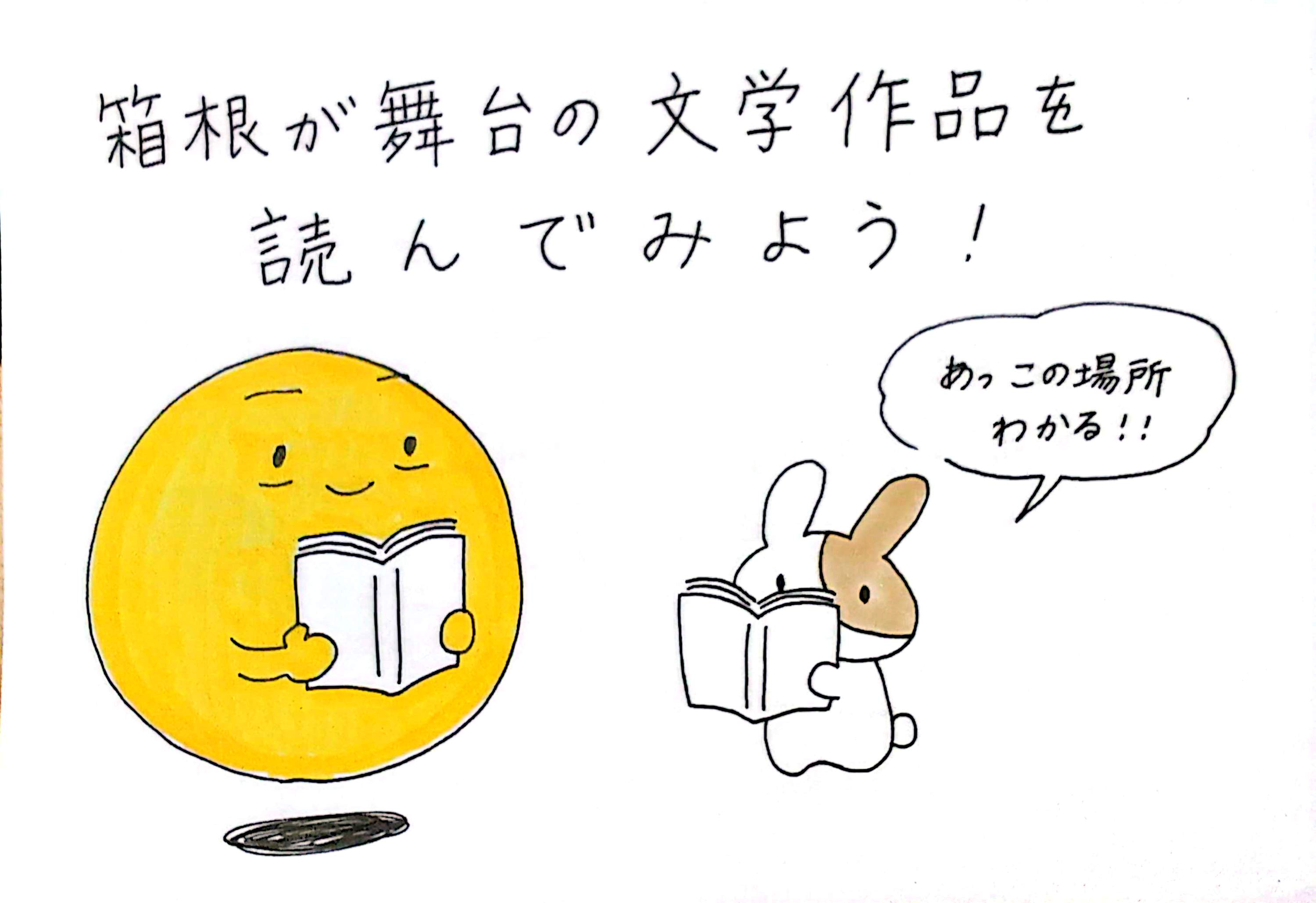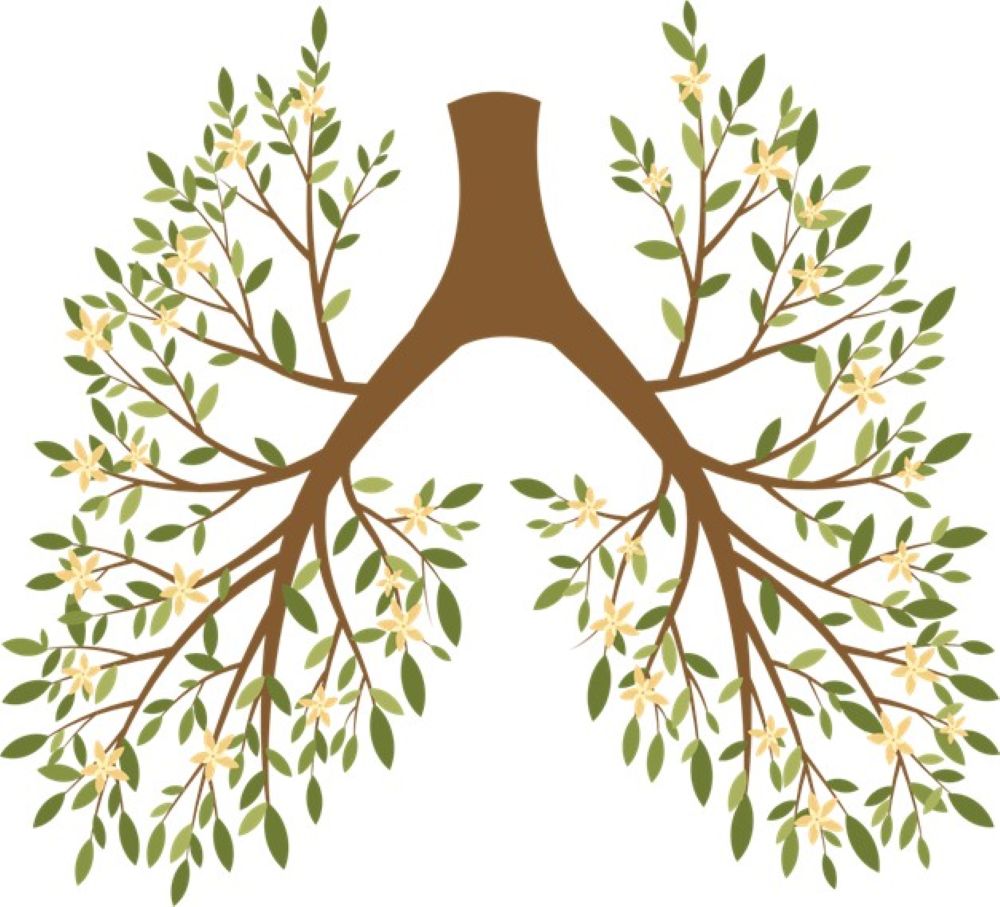過日、早春の3/17(日)、箱根町宮城野の早川沿いにて、「はこじょマインドフルネス森林セラピー」の授業を行いました。
マインドフルネスや森林セラピーについて、そのときにお伝えしたこと、さらに当日お伝えしきれなかったことも含めて、あらためてポイントをまとめてお伝えします。
是非多くの方々に、箱根の良さはもとより、マインドフルネスや森林セラピーについての理解をいっそう深め、心と身体の健康のためにお役立ていただければと思います。
ポイント1.とらわれからの切り替えスイッチ
マインドフルネスのポイントはいくつかありますが、心理カウンセリングを専門としている筆者からみた場合、マインドフルネスとは「とらわれからの切り替え」をしやすくすること。心がとらわれている状態から切り替えて、楽になり、心が本来持っている力をいきいきと発揮できるようにしていくことです。
裏を返せば、私たちは日々何かにとらわれているとも言えるでしょう。ときに心はとらわれ過ぎて、とらわれから抜け出せないというとても苦しい状態になってしまうこともあります。
こういったときにも、とらわれからの切り替えスイッチとしてマインドフルネスを知り、身につけていくと、とても役に立つことと思います。
ポイント2.思考と視覚に偏ったバランスを調整していく
筆者が考えるマインドフルネスのポイントをもうひとつあげます。
普段私たちは、五感で感じることよりも、頭で考えることの方が多いのではないでしょうか。また、五感を使うとなると、スマホ・パソコン・テレビ・文書等から、目を使って情報を得ることが多くなるでしょう。これらは現代社会特有の偏りと言えますが、ともすると私たちは思考優位となり過ぎたり、目を酷使することが多くなったりします。
マインドフルネスを実践していくことで、この偏りを調整して心身のバランスを良くしていくことができます。
気づきを深めていく、立ち止まって観ながら
とらわれから切り替えていくためにも、偏ったバランスを調整していくためにも、まず一番に必要なことは、私たち自身が今どういった状態にあるのか、何がどんな風に起こっているのか等についての気づきを深めていくことです。これがマインドフルネスのベース(土台)です。
そして、気づきを深めていくためには、普段私たちが特に意識せずに自動的に行なっている、心や身体の営みを、立ち止まって観ていくことが有効です。
この「立ち止まって観る」ことを行う瞑想を、文字通り止観瞑想と言いますが、マインドフルネスといえばこの瞑想。姿勢を整え、楽にして、目を閉じ、呼吸に注意を向けることから始めていきます。
五感で観る。マインドフルネスと森林セラピーの共通点
立ち止まって観ると言いましたが、この「観る」ということが、マインドフルネスの大きな特徴です。
日本マインドフルネス学会では、「観る」について、以下のように定義しています。
【観るとは「見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる、さらにそれらによって生じる心の働きをも観る」という意味】
つまり、「観る」とは五感を使って観るということ。ここが森林セラピーとマインドフルネスの相性がとてもいいゆえんです。両者とも五感をよく使うということが特徴です。
エクササイズ、スローモーションのように
マインドフルネスでは瞑想以外にもさまざまなエクササイズを行い、自分は今何を見ているのか、何を聞いているのか、何を嗅いでいるのか等々、五感を使って自分が今まさに体験していることに気づきを深めていきます。
普段、ルーティンのように流れるように行なっている日常の一コマ一コマを切り取り、とてもゆっくりと進めていきつつ、五感を研ぎ澄まして観ていくのがマインドフルネスです。それはあたかもストップモーションやスローモーションをするような要領です。
さらにマインドフルネスがマインドフルネスらしいところは、「五感で観たことによって生じる心の働きをも観る」という点にあります。五感で観たことで心・身体・頭がどのように変化しているのかも、じっくりと観ていくことがマインドフルネスの特徴です。
すべての苦痛からの解放
マインドフルネスには、気づきを深めたり、リラックスしたりといった効果もありますが、究極的にマインドフルネスが目指しているのはどういったことでしょうか? 目指しているのは、心がとらわれて苦しんでいる状態からの解放です。ストレスコーピングを専門とする伊藤絵美(臨床心理士)氏の言葉を借りると、つまりそれは「手放す」こと。 「マインドフルネスとは、自らの体験にリアルタイムで気づきを向け、評価や判断を加えずにそのまま受け止め、味わい、手放すこと」と、伊藤氏は言っています。
マインドフルネスは、般若心経と同じことを目指しています。般若心経では次のように言っています。
「この世の中にあると思っている苦痛、それは実在しない。すべては自分の心の中で創り上げた幻想。それを深く理解することで、全ての苦痛から解放されるだろう」と。
*以前の記事 『マインドフルネス 〜悩み・苦しみを作り出しているものは?〜』
http://hakojo-lab.jp/media/2018/04/10/162
今回特に取り上げていませんが、マインドフルネスには「あるがまま」というポイントもあります。よろしければ以前の記事もご参考にしてください。
この記事を書いた人
新行内勝善(しんぎょううち かつよし)
心理カウンセラー、森林セラピスト、精神保健福祉士。
東京メンタルヘルス社にて、メンタルヘルス相談や、心の病からの職場復帰をサポート。
職場復帰プログラムでは森林セラピーを導入。
また、スクールソーシャルワーカーとして小中学校の子どもたちと家庭をサポート。