
皇居お濠と皇居東御苑、2月の森林浴
2026年2月14日。快晴。気温は10℃から14℃。一週間前の大雪が嘘のように、空は澄みきり、光はやわらかく、空気は透き通っていました。2月の森は、寒さの中にあるのではなく、静けさの中にあります。そし...

清里の森で育つ、未来へのまなざし この記事を書いた人 高田裕司(たかだゆうじ) 中小企業診断士、森林セラピスト、キャリアコンサルタント、森林インストラクター 親子、小学生から高齢者までの様々な方のご案内を担当。NEALインストラクターでもある。
〜小金井市立小学校での森林ESDの取組〜
森林と教育を結びつける試みは「森のようちえん」など、さまざまな形で各地で行われています。
筆者は山梨県清里で、小金井市立小学校6年生の林間学校を通じて、3年間「森林ESD(持続可能な開発のための教育)」に取り組んできました。
ここでは、その活動の様子を紹介します。
1.森林ESDプログラム導入の背景と主な活動
小金井市教育委員会は、夏休みの2泊3日の林間学校を「行くだけ」「見るだけ」「登るだけ」の体験から、「子どもの人生が変わる林間学校」へと進化させることを目指しています。
林間学校では、間伐体験など実際の作業を行い、事前と事後の学習とつなげることで、子どもたちが「森林を守ることは自分たちの生活を守ること」だと感じられるようにしています。
また、「林業」という仕事の存在やその重要性も、体験を通じ学びます。
こうした目的から「森林ESDプログラム」が導入されました。
主な活動は、間伐体験と探究学習です。
林業会社の方と協力し、実際にカラマツを伐採し、4メートルの丸太に加工するなど、本物の林業に触れることができます。
その後は、清里の森をフィールドに、調査や間伐材を使ったベンチやテーブル作りなど、探究学習に取り組みました。
2.学びの内容と支援者の役割
事前に学校で、これまで森林や生物などについて学んだことを振り返ります。
そして、今回の林間学校で「やってみたいこと」ごとに10人程度のグループを作ります。
あらかじめグループで「何をどう行うのか」を相談し、それを現地で活動を実践。
学校に戻ってからは、学んだことを5年生や保護者に発表します。
筆者は現地清里でこのグループを担当し、子どもたちのやりたいことを受け止め、実現できるようサポートします。
指導は道具の使い方や安全に関わることなど最小限にとどめ、子どもたちが主体的・対話的に学びを深められるよう声掛けと情報提供を心がけました。
3.活動の様子〜多様な調査体験〜
筆者が担当したのは「虫・きのこ」「動物」「昆虫」「植物全般」の4グループで、それぞれ2時間半程度の活動でした。
標高約1,350メートルの清里の森入り口で、子どもたちに「小金井との違い」を尋ねると、
「涼しい」「自然が多い」「山や森がある」といった声が聞かれました。
小金井市との標高差は約1,300メートルで、気温や空気の違いもみんなで確認してから森に入りました。
森の中では、
「ここにもあるよ!」
「あっ、見て見て」
「匂うけど、どんな匂いか表現できない」
「この草は初めて見る」
「この木、誰かがかじった跡がある!」
「これは動物の足跡かも!」
など、子どもたちは発見の連続です。
新しい発見に目を輝かせ、昆虫やきのこが好きな子も苦手な子も、思い思いに自然と向き合いました。
予定通りにいかないこと、期待していた生きものに出会えないこと、さまざまな「想定外」に直面しながらも、仲間と相談し協力して次のステップに進みます。
森は多様な生きものが生活する場所であり、私たちはその暮らしに「お邪魔させてもらっている」存在です。
森の命の循環に気づくことが、ESDの入口となります。
最後に、気づいたことや苦労したこと、今後調べたいことなどを記録し、感想を発表しました。
多くの子どもが、小金井では見られない発見や経験を話してくれました。

4.活動の様子〜間伐材活用〜
今回担当した「ベンチづくり」と「階段づくり」も、それぞれ2時間半の活動です。
森で伐採したカラマツの丸太を使い、グループごとに設計図を描き、みんなで「誰かの役に立つもの」を考えて作りました。
ベンチづくりでは、「みんなが座りやすいものを作る」という目標でした。
材料となる丸太を皆で運び、それと設計図をもとに作るものを最終確認しました。
すると設計図に記載の丸太を半分にする作業が時間内には終わりそうにないことに気がつきました。
急きょ、どうするのかを仲間と話し合い、変更した方向性で作業を開始。
そしてインパクトドライバーとダボの使い方をこちらから伝え作業を継続。かすがいも使いました。
途中で雷が鳴り始め屋外から体育館へ移動するトラブルもありましたが、無事に完成させました。
さらに階段づくりでは、こちらが指定した場所で作業を行いました。
間伐体験する場所から丸太を運ぶ通り道の中で、下りの傾斜がある場所です。
ここに階段があると皆が運びやすくなります。
道具を持って、その場所に行き、丸太を必要な長さにノコギリで切るグループと階段にする場所をスコップで整備するグループに分かれて作業開始です。
そこから想定外のことがいろいろとありました。
「簡単にできると思っていた。
でもやり始めると根っこが多くスコップで段を作ることができなくて、「無理だ。できない」と思った。
でも1段できてから、皆で協力や声掛けをしながら階段を作ることができた」
「無理かも」と思いながらも、協力して6段の階段を作り上げました。
人間は長い間、森林の中で暮らしてきました。
森林浴は自律神経を整え、ストレスを軽減する効果があることはよく知られていますが、
それに加えて、多様性あふれる自然に囲まれることで得られる学びや気づきは本当に多いと強く感じました。
この後、子どもたちが学校でどんな発表をしてくれるのか、とても楽しみです。

植物の生態やネイチャーゲームを取り入れた臨機応変な対応には定評があります。
経営コンサルタントとして、農業者支援を数多く実施。50坪ほどの家庭菜園での野菜づくりとランニングが趣味。

2026年2月14日。快晴。気温は10℃から14℃。一週間前の大雪が嘘のように、空は澄みきり、光はやわらかく、空気は透き通っていました。2月の森は、寒さの中にあるのではなく、静けさの中にあります。そし...

森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

最近、「40代前半で生理が終わった」「生理周期が乱れてきた」そんな声を、周りで聞くことはありませんか。アーユルヴェーダでは45歳〜55歳の間に更年期の症状が出やすいと言われていますが、生理の終わり方や...

リトリートとは、もともと英語で「退く」「退避する」「静かに引きこもる」という意味があります。宗教的な修行・瞑想(スピリチュアルリトリート)でも古くから使われてきました。たとえば、禅の修行では「接心(s...
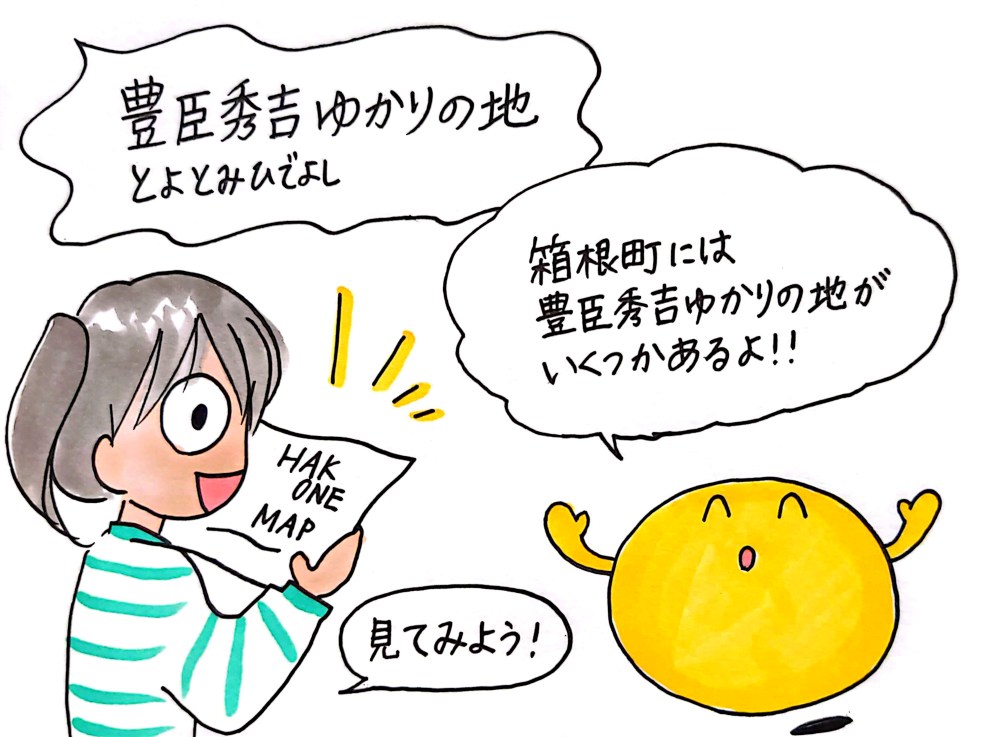
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...