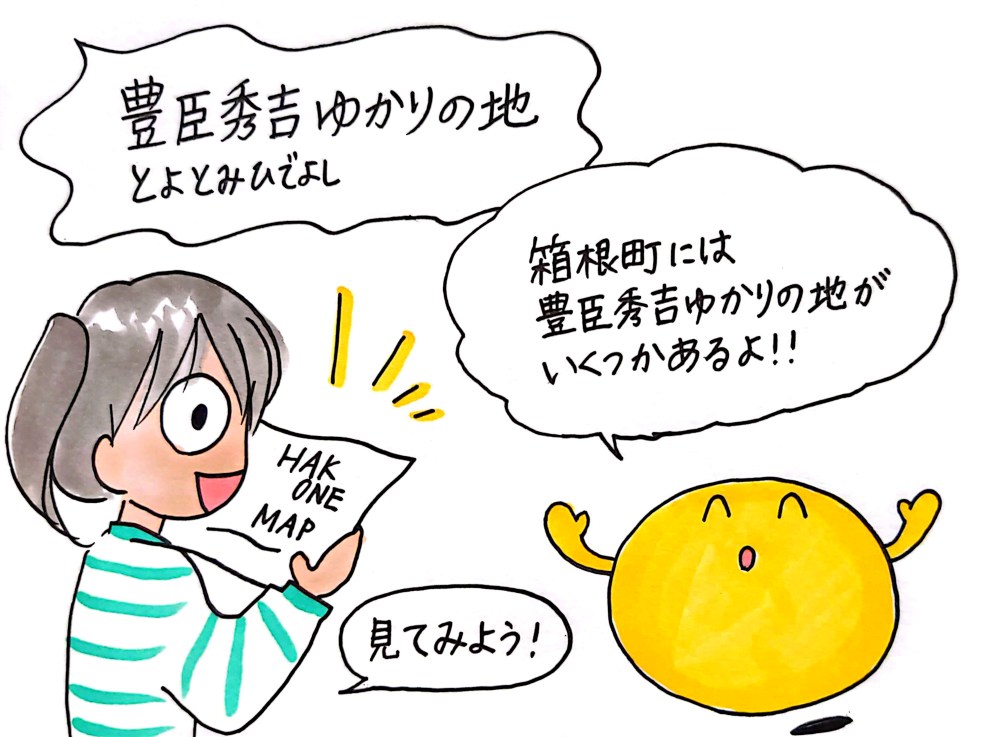
箱根町には豊臣秀吉ゆかりの地がいくつかあるよ!
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

秋の箱根といえば、ススキ野原の美しさが有名です。
今回は前回に引き続き、秋の七草のひとつである秋の代表の草「ススキ」のお話です。
ススキ(薄/芒)イネ科ススキ属、多年草。日本全土の野原、道端の日当たりの良いところに生えます。
名前の由来は諸説ありますが、「すくすく育つ(立つ)木」。高さがあるので木のように見えるとか。
うーん。見えますかね?? 穂を馬の尾に見立ててつけられた別名「尾花」、茅葺き屋根の材料で刈って茅葺にするから「茅」という別名も。
こちらも「クズ」と同様、北アメリカに帰化しています。
ススキに似た植物で、同じように茅葺き屋根の材料になる「オギ」があります。見分け方ですが【ススキ】水中に生えない。
たくさん茎がまとまって株立ちする。芒(ノギ)がある。葉の縁でしばしば切れる。
穂が金色。【オギ】水辺、湿地に生える。大群落を作る。ススキより穂がフサフサしている。
芒がない。穂が銀色。下葉は早く枯れる。芒とは、タネからぴょこんと生えている一本の髭みたいに見えるもののことを指します。

茅(カヤ)という植物は存在しません。ススキやオギ、ヨシ(アシ)などのイネ科の総称なのです。
昔はカヤ場というススキの群落があり、人が毎年、刈り取り、火入れ(野焼き)し、建築材料として生産していました。
東京にある「茅場町」はまさにカヤ場の名残の名前ですね。
冬の枯れ始めた頃に刈り取り、数日間乾燥させて貯蔵します。材料によって耐久性も違い、「ススキ・ヨシ」が20〜40年、「麦わら」が10〜15年、「稲わら」が5〜7年ほど。
ススキで作る屋根は高級品だったのですね。

ススキをはじめ、イネ科の植物にはガラス質が入っています。
プラント・オパールと呼ばれます。
わかりやすいのが、ススキの葉の縁のギザギザ。何度手足を切ったことでしょう……。ガラスのトゲだもの、そりゃ切れますね。
ガラス質=ケイ素。土から吸収し体内に溜め込み、乾燥や害虫から身を守っています。
ススキの茎はコンクリートと同じ耐久力があるとか。それは言い過ぎな気がしますが(個人的な意見です)。
ガラス質ってガラスじゃないの??と思ったら、ススキからガラスを作っているサイトを見つけました。私のいつかやってみたいリストに追加されました。

十五夜の中秋の名月で、縁側にススキとお団子をお供えします。
名前の由来の「すくすく育つ木」。
稲穂のかわりに飾り、収穫の感謝とイネがすくすくと育つように翌年の豊作を願ったそうです。
また、空洞の茎は神様の宿り場。ススキの葉のガラス質のトゲは魔除けになるとも言われ、悪霊や災いなどから守る意味もあったようです。
はこじょセラピーデイズでは「ススキでホウキ」というWSをさせていただいたのですが、ホウキも呪具や儀式具として使われていたこともあり、毎年ススキでホウキを作って使うと家の中を「払う」ことにも繋がるのではないかと私はオススメしております。

若い穂を天ぷらにして食べることもできるそうです。
天ぷらはまだ未食ですが、穂のお茶はなかなか美味です。
全草に「利尿・解毒・風邪・高血圧」の薬効があるとか。一時期はセイタカアワダチソウに追いやられていたススキ。
近年ではぐんぐん盛り返していると聞いています。ただしススキが生えてしまうと他の植物が生えにくくなります。
根は50cmは掘り返さないと駆除ができないほど厚く、そして拡がります。
もちろんタネでも増えます。庭先に植える場合は注意が必要です。最後に大切なこと。箱根のススキですが国立公園の植物は採取禁止です。気をつけてくださいね!

この記事を書いた人

はやぶさ きみ枝(はやぶさ きみえ)
『雑草研究所』所長
グラフィックデザイナー。猫飼い。イベントや観察会を通して、植物の面白さを多角的視点で発信し実践する生活をしている。
雑草研究所
FB:https://www.facebook.com/zasso.labo
twitter:https://twitter.com/zasso_labo
Instagram:https://www.instagram.com/zasso.laboratory/
最近書いた記事
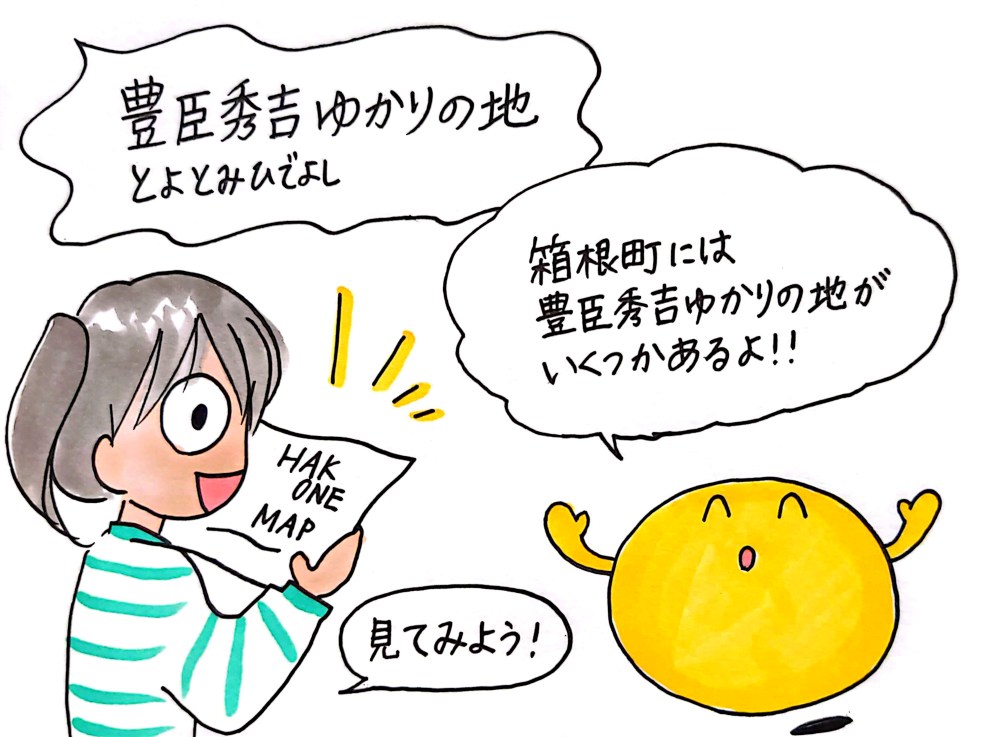
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...