
病気が教えてくれた「自然治癒力と予防医療」
予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

 ブルーベリー状の果実。摘んだ指先を赤く染めて
ブルーベリー状の果実。摘んだ指先を赤く染めて 蔓から飛び出る巻きひげを他の植物に絡めながら這い上がっていく
蔓から飛び出る巻きひげを他の植物に絡めながら這い上がっていく ほかの植物にかぶさるように伸びる
ほかの植物にかぶさるように伸びる 山ぶどうのジュース
山ぶどうのジュース 夏はきゅうりやなす、ゴーヤなど。冬はみかんなども一緒に添えてみては
夏はきゅうりやなす、ゴーヤなど。冬はみかんなども一緒に添えてみては山ぶどうというと、フルーツばかりではありません。昔からその葉も蔓も大切で、山あいの暮らしに欠かせない素材でした。
葉っぱは手のひらほどの大きなものもあってお皿になりますし、エリアによっては葉を草餅の中に混ぜこんだり、乾燥させてお茶にしたりと自由自在!
先人の植物遣いの知恵はほんとうに見事だなと思います。
そしてときに20mを超す高さになる蔓。
太いものでは直径10cmレベルのものもあるそうです。
この蔓ごと採取して、内・外皮を剥いで天日乾燥させたあと、改めて水に浸けて柔らかくし、太さを揃えるためにカットして材料を揃えます。
そこからようやく型に沿わせて編み上げていきます。皮自体はとても丈夫ですが、思った以上に軽くしなやかな印象です。
素材とともに大切なのは、細やかで確かな加工の腕。
先ほどの山菜料理に共通しますが、たくさんの手間のもとに日常のカゴづくりがなされてきたことに、改めて気づかされます。 太い蔓
太い蔓
 型を土台に編み込む
型を土台に編み込む 山ぶどうの真新しいカゴ(あじろ編み)。使いこむうちに黒く艶を増す
山ぶどうの真新しいカゴ(あじろ編み)。使いこむうちに黒く艶を増す
以前、山形の羽黒山を案内していただいた山小屋のご主人に、「(このエリアで)蔓を採取するのは夏の土用の1週間のみ」だと教えていただきました。
天然素材は有限ですから、質の良いものの採取も年々厳しくなっているし、腕の良い作り手も減っているそうです。
もし街なかで山ぶどうのバッグを見かけたら、この蔓は山の中でどんなふうに育っていたのだろう?
どんな方が編んだのだろう?と想像してしまいそうですね。大切にしていきたいものが、この国にはたくさんあります。
<ご協力いただいた取材先>
出羽屋(山形県西川町)http://dewaya.com/
宮本工芸(青森県弘前市)https://goo.gl/4DTacz
この記事を書いた人

平川 美鶴 (Mitsuru Hirakawa)
和ハーブライフスタイリスト
植物民俗文化研究/(一社)和ハーブ協会 副理事長
8月2日“ハーブの日”生まれ。「和ハーブ」と日本人の関わりを、歴史・文学・薬効・自然風土・産業などから調査研究。講師業、商品企画開発、実践ワークショップを通じ、自然の恵みと共にあった先人の尊い知恵を生かし、未来へどう届けるかを考えるメッセンジャー。共著『あなたの日本がもっと素敵になる 8つの和ハーブ物語 ~忘れられた日本の宝物~』(産学社)、『和ハーブ にほんのたからもの』(コスモの本)
一般社団法人 和ハーブ協会(Japan Herb Federation) http://wa-herb.com
最近書いた記事

予防医療という言葉をご存知でしょうか?私は、知識としてではなく自分の身体を通して知ることになりました。看護師として夜勤専従で働き、コロナ禍という強い緊張の中に身を置き続けた末に、私はバセドウ病を発症し...

箱根の1月〜3月は、寒く雪が降る日もありますが、晴れる日がとても多いです。標高の低い箱根湯本と山間部(仙石原など)では気温差があり、平均気温では約4℃違います。 この時期の箱根の森林浴にはどのような特...

冬至を過ぎると、暦の上では「陽が生まれる」とされます。日照時間はわずかに伸び始め、一見すると冬は折り返しを迎えたようにも感じられます。しかし、身体の感覚は正直です。冷えはますます増して夜は長く、空気は...

12月中旬、東京都立林試の森公園で森林浴を行いました。冬に入りつつある時期ではありますが、この日の森にはまだ秋の気配が残っていました。葉を落とした木々の間を歩くと、空気は澄み、音は少なく、自然と呼吸が...
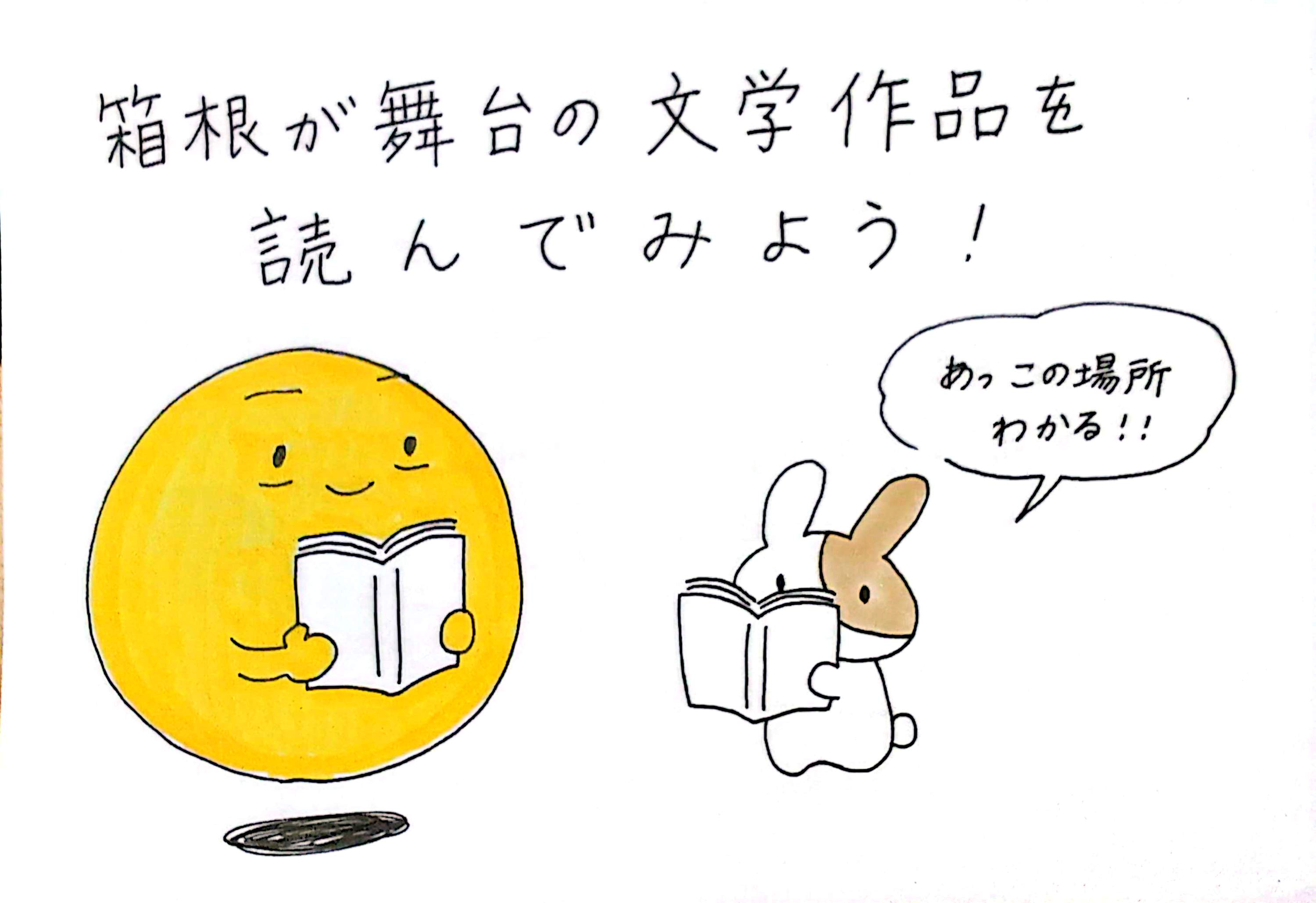
森子の日常の何気ない箱根ライフを、はこねのもり女子大学学長が味のあるイラストで紹介! この記事を書いた人 天野 湘子(あまの しょうこ) はこねのもり女子大学学長 箱根町仙石原出身 幼少期~小学2年ま...