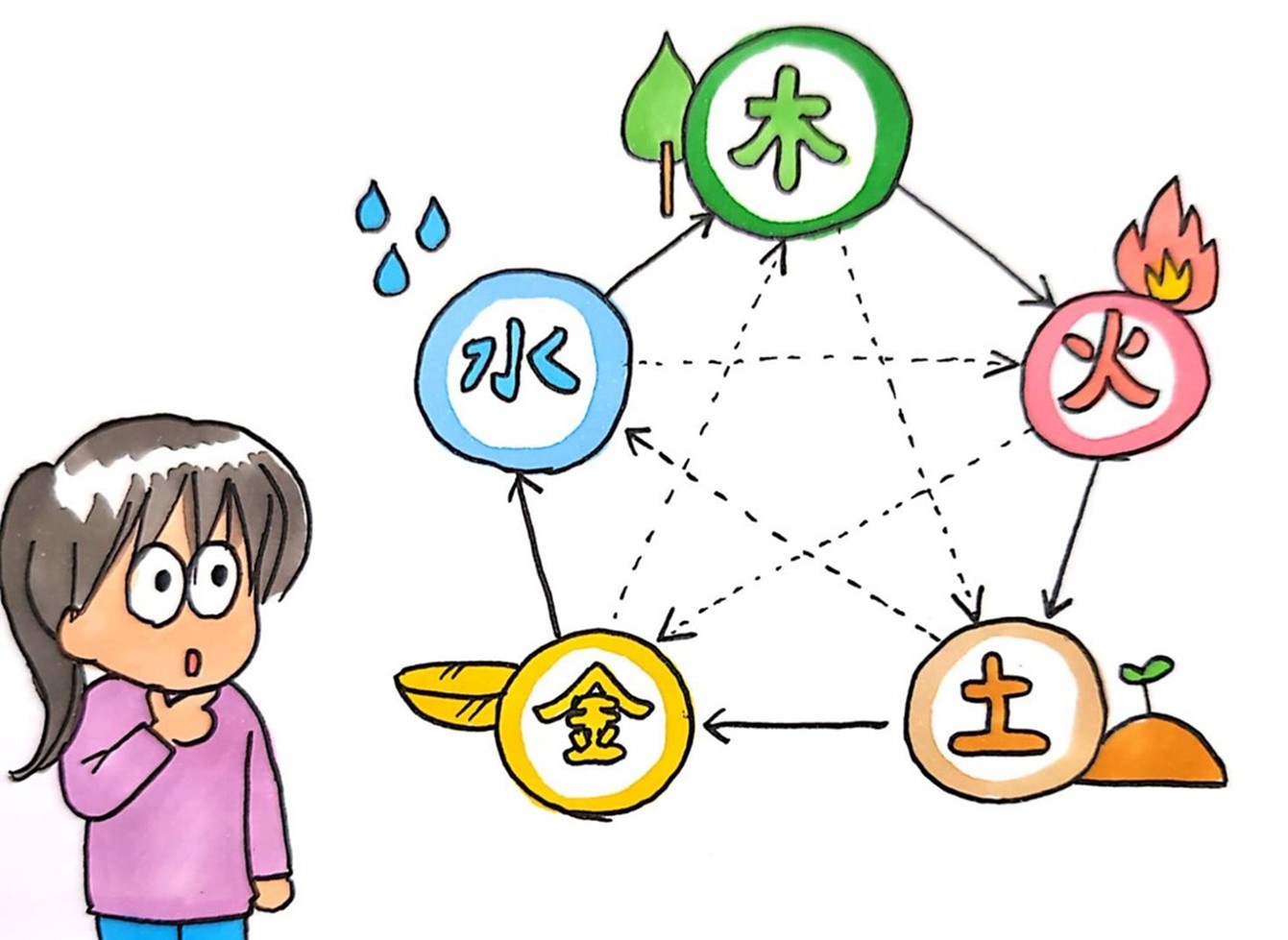さてみなさんは今巷でブームの「マインドフルネス」をご存知でしょうか?
「マインドフルネス」は、はこねのもり女子大学でも人気授業のコンテンツのひとつですが、この効用にはビジネスの分野でも注目が集まっていて、グーグルは早くから瞑想に着目し「マインドフルネス」を独自にプログラム化して、社員研修に取り入れました。そういった動きは、インテル、フェイスブック、フォードなどにも見られ、現在日本でも実践が広がっています。
最近は企業だけでなく小学校などの教育機関でも取り入れられ、子どもたちの授業中の集中力アップ、けんかや問題行動の減少といったメリットも認められているそうなのです。
そもそも「マインドフルネス」とは?

「マインドフルネス」とは本来、いまこの瞬間に起こっている感覚や感情、思考に気づき、ありのままに受入れること。
そのような状態になるための瞑想が、「マインドフルネス瞑想」です。
※「図解マインドフルネス瞑想がよくわかる本」 監修 有光興記 講談社より人生に悩みはつきものですが、心が軽くなる方法があるとしたならぜひ試してみたいと思いませんか?
私たち人間は、なにをする時にもさまざまな事を思ったり考えたりして、状況を複雑にし、悩みを深めていきがちです。
そんな心の働きが複雑になっていて、なにかと想い悩む状態になっている人も、日常に「マインドフルネス瞑想」を取り入れることによって、心の本来の機能を発揮できるようになり、そうすれば心や脳もスッキリして集中力や行動力もアップするそうなのです。
「でも、マインドフルネスってどうやってやるの?」
「なんだかむずかしそう!」
「瞑想なんて簡単にできないのでは?」
「良さそうだけど毎日は続けられないのでは?」
ひとりでやるにはうまくできるのか不安ですよね?
そこでみなさんにおすすめしたいのが「マインドフルネス瞑想」の基本的な手法「呼吸の瞑想」にアロマをとりいれてみる方法です。
なぜ「マインドフルネス」にアロマがおすすめなのか
みなさんは香りを嗅いだとき一瞬でいい気分になったりまたその反対に不快になったり、または昔のことを思い出したという経験はありませんか?
というのも香りの刺激が脳へ伝わるまでの時間はなんと0.2秒以下、痛みなどが伝わるまでの時間は0.9秒あるいはそれ以上だと言われています。
つまり痛みを感じるよりも早く香りの刺激は脳に伝わるということなのです。
また精油を嗅ぐとエンドルフィン、セロトニン、アドレナリンなど多幸感や情緒の安定、心を活気づける、鎮静などの効果をもたらす脳内の神経伝達物質が分泌されることもわかっています。
香りによって刺激される大脳辺縁系、視床下部、下垂体といった脳の部位は、心の影響を受けやすく、感情が安定していると円滑に働き、病気にもなりにくいのです。
昔から瞑想や座禅には、その場を浄化し意識を集中させるためにお香が焚かれていました。
香りのチカラを借りれば一瞬でスイッチを切り替えることができるのです。
ぜひ自分が心地よく感じ、気持ちが休まる香りを選んで、マインドフルネス瞑想へのスイッチをONしてみるのはいかがでしょうか。
では次に「マインドフルネス瞑想」におすすめのアロマをピックアップして
ご紹介したいと思います。
精油を選ぶ時のポイントですが、香りにはそれぞれ個人の好みがありますので、自分が今「心地よい」と感じるものを選ぶことです。
【目的別】「マインドフルネス瞑想」におすすめアロマ5選

*グランディングしたい(落ち着きたい)時は「フランキンセンス (カンラン科)」イエスキリスト誕生の贈物として没薬とともに捧げられた香りでもある。
【香り】甘くウッディな落ち着きのある澄んだ香り。わずかにレモンのような香りも。
【作用】鎮静、呼吸器系機能調整、免疫強化 など
*集中力を高めたい時は「ローズマリー (シソ科)」 古くから若さを取り戻すハーブとして、また記憶力を高めるハーブとして知られている。
【香り】すうーっと爽やかなハーブ調のフレッシュな香り。
【作用】頭脳明晰、記憶集中力強化、肝臓強壮 など
※ てんかんの方は使用を避ける。
* 幸福感を感じたい時は「クラリセージ (シソ科)」 クラリセージの名前はラテン語の「明るい」「澄んだ」を意味するクラルスに
由来する。女性特有のトラブルを緩和する作用がある。
【香り】甘くてナッツのような、スパイシーでパウダリーな印象の香り。
【作用】鎮静、緩和、抗うつ、ホルモン調整 など
※妊娠中は使用を避ける。使用後にアルコールを飲むと悪酔いすることがある。
*自己肯定感を育みたい時は「イランイラン (バンレイシ科)」 イランイランの語源はタガログ語の「花の中の花」を意味する。インドネシアでは新婦夫婦のベットの上にイランイランをまく風習がある。
【香り】エキゾチックでフローラルな官能的な香り。甘く陶酔させる
【作用】精神高揚、抗うつ、ホルモン作用 など
* 創造力を養いたい時は「ベルガモット (ミカン科)」 古くから香料として使われ「ケルンの水」の主要原料だったといわれている。
またアールグレイ紅茶の香りづけとして有名。
【香り】甘さの少ない爽やかな香り。柑橘系の中でも大人向きで辛口。
【作用】精神安定、緩和、消化機能調整、抗菌 など
※光毒性がある。皮膚に使用後は紫外線を避ける。
実践!呼吸の瞑想×アロマで心と脳を軽くしてみよう

お好みのアロマを選び、専用のディフューザーなどで香らせて呼吸の瞑想にトライしてみましょう。
(ディフューザーをお持ちでない場合はマグカップにお湯を入れ、そこへ精油を2〜3滴たらしてもOKです)
《基本的な「呼吸の瞑想」のやり方》 〜朝起きて、または夜寝る前の10分間〜
・楽な姿勢で息を吸ったり吐いたりすることに意識を集中します。
・呼吸するときのお腹の動きに意識を向け、難しければ最初は手を当てて感じるのも良い。
・雑念がわくこともありますが、呼吸に意識を向け続けます。
・ そうして体の感覚に気づくと、思いや考えに振り回されなくなっていくそうなのです。
※ただしコンディションによっては症状が悪化することもあるそうなので、体調に異変を感じたら無理せず中止してください。
その日の気分や、自分が必要とするアロマの効能や効果を取り入れながら、「マインドフルネス瞑想」でゆったりと呼吸しながら気持ちをゆるめて心にゆとりを持つことで、よけいな考えに振り回されないありのままの自分で過ごせたらいいですね。
“マインドフルネス瞑想をやってみたい!”と思われた方は、2019年3月17日(日)開催「はこじょマインドフルネス森林セラピー」の授業にて、いろんなアプローチで皆さんと一緒にマインドフルネスを体験しますので、ぜひ箱根に遊びにいらしてください。
心よりお待ちしております!
〈お申込・詳細はこちらから>
http://hakojo.com/index.php?page=event&id=116参考文献
「図解マインドフルネス瞑想がよくわかる本」 監修 有光興記 講談社
「スタンフォード大学 マインドフルネス教室」スティーヴン・マーフィ重松 坂井純子 訳 講談社
「いちばん詳しくて、わかりやすい!アロマテラピーの教科書」著 和田文緒 新星出版社
「ハーブとアロマの心理療法」山本裕美 著 東京堂出版
この記事を書いた人
木村 容子
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター/JAMHA認定メディカルハーブコーディネータ/神奈川県 県西未病観光コンシェルジュ/(一社)はこねのもりコンソーシアムジャパン代表理事
こころとからだを癒す箱根の森に魅せられ「はこねのもり女子大学」の運営に携わる。
ポータルサイト運営会社にて医療機関の取材を重ねるうちにセルフケアの大切さを実感。以前から興味のあった植物療法に注目し、アロマテラピーとハーブの資格を取得。毎日の生活に楽しく気軽に植物のパワーを取り入れながら健康でビューティー&ハッピーに過ごすことを目指す。一男一女の母。